特養の医療対応はどう変わったのか?
特別養護老人ホーム(特養)は「生活の場」としての役割を持っています。
そのため、入居者に体調の変化があれば、基本的には病院での受診が前提です。
ところが、私自身の介護経験を振り返ると、かつては施設で点滴や採血を行うのが当たり前でした。看護師が処置を担い、「なるべく受診させない」というのが現場の雰囲気だったのです。
では、なぜ今は「受診を優先し、場合によっては家族が付き添う」流れに変わってきているのでしょうか。
この記事では、特養の医療対応が昔と今でどう変わったのか、その背景と実態を解説します。
施設選びや待機中の動きで迷ったら、状況を整理して次の手順を提案できます
文章相談はコチラから👉介護の悩みを文章で整理し、次の手順を提案します 介護の悩みを吐き出してください。(ココナラ)
特養は「生活の場」|病院との違いをまず知っておこう
特養は病院ではなく「生活の場」です。
そのため医療依存度が高い方であっても、日々の生活の中で体調の変化があれば、必要に応じて受診することが求められます。
- 嘱託医(配置医)が定期的に往診
- 協力病院と連携して検査や治療を実施
この仕組みで、入居者の医療ニーズを支えています。
昔の特養:施設内で点滴や採血まで対応していた
私の経験では、点滴や採血といった処置を施設の看護師が実施することは珍しくありませんでした。
「できることは施設で対応し、受診はなるべく避ける」というのが当時の雰囲気だったのです。
結果として、家族も安心して任せられる側面はありましたが、その一方で看護師の負担は相当大きかったと思います。
今の特養:なぜ病院受診や家族付き添いが増えているのか?
最近は、次のような背景から「病院受診にシフト」する流れが強まっています。
- 職員不足:受診の引率まで手が回らない
- 法的リスク管理:医療行為の線引きが厳格化
- 入居者の重度化:看取りや医療依存度が高まっている
結果として、施設内でできる処置は限定的となり、「受診+家族付き添い」という体制を取る施設も出てきています。
データで見る特養の受診対応|誰が付き添うの?
ある調査では、特養入居者が外来受診する際の付き添いは:
- 看護師:約69%
- 生活相談員:約10%
- 家族:約8%
- 介護職員:約7%
という結果でした。つまり、家族付き添いは少数派ではあるものの、ゼロではなく実際に存在します。
また、救急搬送時には**85%の施設が「家族に来てもらう」**と回答しており、職員不足を背景に家族協力を求める実態も浮かび上がっています。
入所前に確認すべき3つのチェックポイント
入所後に「思っていたのと違う」とならないために、次の点をチェックしておくことが大切です。
- 受診時の付き添いは誰が行うのか?(職員/家族/外部委託)
- 協力病院の診療範囲や往診体制はどうか?
- 救急時の搬送ルールは?(同乗できるのか、家族連絡はどうなるのか)
重要事項説明書や契約書に記載されていることが多いので、事前に確認すると安心です。
まとめ:特養は病院ではないからこそ、受診体制の理解が大切
昔、受診付き添いとなると介護職が行ってることが多かったように思います。
受診前に利用者の情報を確認して、Drに受診の経緯や状況を話して、診察の内容を聞いてくる形です。
しかし、先のデータ同様、今の施設では受診には看護職が行っており、とても適任だと感じます。
なぜなら、医療面で素人である介護職が受診に行っても、聞くべきポイントがわからず、必要事項を再度病院に確認するケースが多く見られました。
介護施設のあり方も、
「施設で点滴や採血まで対応」が当たり前だった時代から、
「病院受診+家族協力」が選択肢に入る時代へと変わってきています。
特養は生活の場であり、医療機関ではありません。
だからこそ、施設と家族がどこまで役割を担うのかをしっかり共有しておくことが大切です。
入所を検討している方は、「受診付き添いの体制」を確認することを忘れないようにしましょう。
介護の悩みを聞かせてください
施設選びや待機中の動きで迷ったら、状況を整理して次の手順を提案できます
文章相談はコチラから
👉介護の悩みを文章で整理し、次の手順を提案します 介護の悩みを吐き出してください。(ココナラ)
〇関連記事
✔【前編】介護保険制度の改正の歴史 ~創設から予防・地域支援2000→2015~ | 介護しよ.net
✔介護の新しい3Kとは?|感謝・工夫・健康でポジティブに働く
✔もう我慢しない。介護職員を守るカスハラ対策と新法のポイント | 介護しよ.net
〇介護情報誌『おはよう21』~1冊から購入できますが、定期購読がおすすめです~
- 最新号が毎月届くので買い忘れなし
- 継続的に学びが積み重なり、スキルアップにつながる
〇 noteを始めました。
こちらでは介護に留まらず、私が普段思う事や、趣味など自由な内容を記事にしていきますので、
こちらから!👉hiro|note
〇 介護しよ.netの公式Lineを作成しました。
介護歴20年のhiroが、介護とお金のギモンに家族目線で答えます。
今なら、登録いただいた方に
『介護のお金で損しない:まず確認する 7 項目チェック』を無料ダウンロードできます。
Line登録はコチラから👇
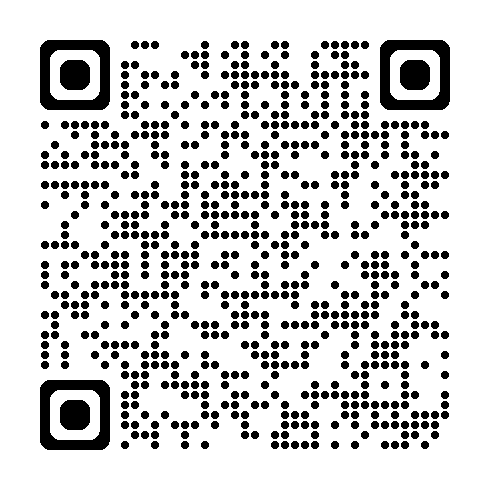


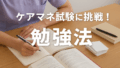
コメント