こんにちは、hiroです。
今回から『変わりゆく認知症ケア』シリーズを
①痴呆→オレンジ | ②新オレンジ→大綱 | ③基本法とこれから
の3部作で公開していきます。今回は第一部となります。
言葉はケアを左右する。侮蔑を含むレッテルから、尊厳を中心に据えた語へ。呼び方の転換は、社会の見方と支援の設計を変えた。ここでは「痴呆」と呼ばれていた時代から、地域を実装で変える「オレンジプラン」登場までを、現場目線で整理する。
痴呆から認知症への変更
かつて今の「認知症」は何と呼ばれていたか。そう、「痴呆」。当時も認知症の人はいたが、家族内に抱え込まれ、表に出にくかった。拡大家族の暮らしや家父長的価値観、そして施設に対する「姥捨て山」という偏見が重なり、当事者の声は届きづらかった。
年表要約:呼び方の転換と政策の起点
- 1986年前後:家族負担中心の視点が主流。医療・介護の連携や地域実装は未成熟。
- 2004年:公的文書で「痴呆」→「認知症」へ用語変更。差別性と妥当性の観点から見直しが進む。
- 2005年:「認知症を知り、地域をつくる10か年」スタート。2009年度を中間年、2014年度を到達目標に設定。段取りは「知る→支える人を増やす→地域に実装」。
- 2013年:次章につながるオレンジプラン(認知症施策推進5か年計画)策定。
一言メモ:用語の転換は“思想の転換”。当事者の尊厳と自己決定を前面に出す合図だった。
10年で何をしたのか
看板だけ立てて終わらせない。街全体を「認知症でもふつうに暮らせる仕様」に作り替えるため、次のパッケージを全国で回した。
仕組み:初期対応と連携の“核”
- 認知症初期集中支援チームの常設 医師の指導の下、保健師・看護師・介護職らが家庭に出向き、受診支援・環境調整・家族支援を短期集中的に実施。配置先は地域包括支援センターや認知症疾患医療センターが標準。
- 認知症地域支援推進員の配置 相談の入口、多職種連携の潤滑油、居場所づくりの仕掛け人を兼務。面で動き、地域資源をつなぐ役。
- 認知症ケアパスの作成・配布 状態に応じて「どの窓口で何を使うか」を一枚で示す市町村版マップ。冊子とWebの両建てで更新。
※ケアパス・・「ケアパス」とは、利用者が“どこで・誰に・いつ・何を”受ければいいかを地図みたいに示した道筋。現場で迷子にならないためのナビの事です。
認知症ケアパスを超ざっくり例 - 気づき→包括へ電話
- →かかりつけ受診・専門医紹介
- →介護保険申請・要介護認定
- →ケアプラン作成
- →通所/訪問/服薬調整/家族教室
- →BPSD出現ならチーム再評価(医師・薬剤師・多職種カンファ)
- →中重度化で短期入所・多機関連携
- →看取り期の意思決定支援
生活インフラ側の実装
- 認知症カフェの定着と輪番開催 当事者・家族・住民・専門職が混ざる場を月1回などで定例化。施設やデイで輪番運営する方式が普及。
- 医療×介護の見える化と相談導線 地域包括をハブに、かかりつけ医・歯科・薬局・訪問系の連絡票やICT連携、迷子SOSネット、見守り協定などを整備。
- まちのユニバーサル改修 サイン計画、照度・対比、音環境配慮、金融・小売の対応マニュアル、公共交通の声かけ訓練等を導入。
普及啓発と協働(“地味だが効く”)
- 住民側の底上げ:認知症サポーター100万人キャラバンなど、ロールプレイを含む研修を商店・銀行・バス会社・学校へ継続展開。
- 介護者支援の標準化:介護教室、レスパイト、ピア支援、ACPの導入と事例共有。在宅看取りを含む実践の横展開。
※認知症サポーター講座で講師をする方をキャラバン・メイトという
「モデル」と呼べるための指標例
- 初期集中支援チームの稼働件数・受診率・BPSD緩和率を年次で公開
- 推進員の常勤換算と年間ケース会議数、カフェ開催回数の公表
- ケアパス配布率と更新頻度、Web掲載の整備
- 医療介護連携の時間軸KPI(初回相談から受診までの中央値、在宅継続率)
- 住民研修のカバレッジ(商店会・交通事業者・学校の受講率)
一言メモ:数字で動き、現場で使われ、住民が巻き込まれているか。ここが“だいじょうぶな街”の見分け方。
つまずきポイントと回避策
- ケアパスが“配っただけ”で使われない 相談現場で使うことを前提に、疾患別と家族向けに版を分ける。年度更新を広報とセットで。
- 推進員のワンオペ化 役割を明文化し、ケース負荷を見える化。委託やボランティア活用で分散。
- カフェが“お茶会止まり” 初期集中支援チームや包括が入り、ケアパス・相談導線と接続させる。次の支援へ自然に橋渡しする設計に。
まとめ:第2部・第3部への橋渡し
10年スパンの国策で、初期支援チーム+推進員+ケアパスを核に、カフェや相談導線、まちの配慮設計までを一体運転する土台が整った。これが2013年のオレンジプランにつながり、2015年の新オレンジプラン、2019年の認知症施策推進大綱、そして2024年施行の認知症基本法へと発展していく。
第2部へ続く、、、
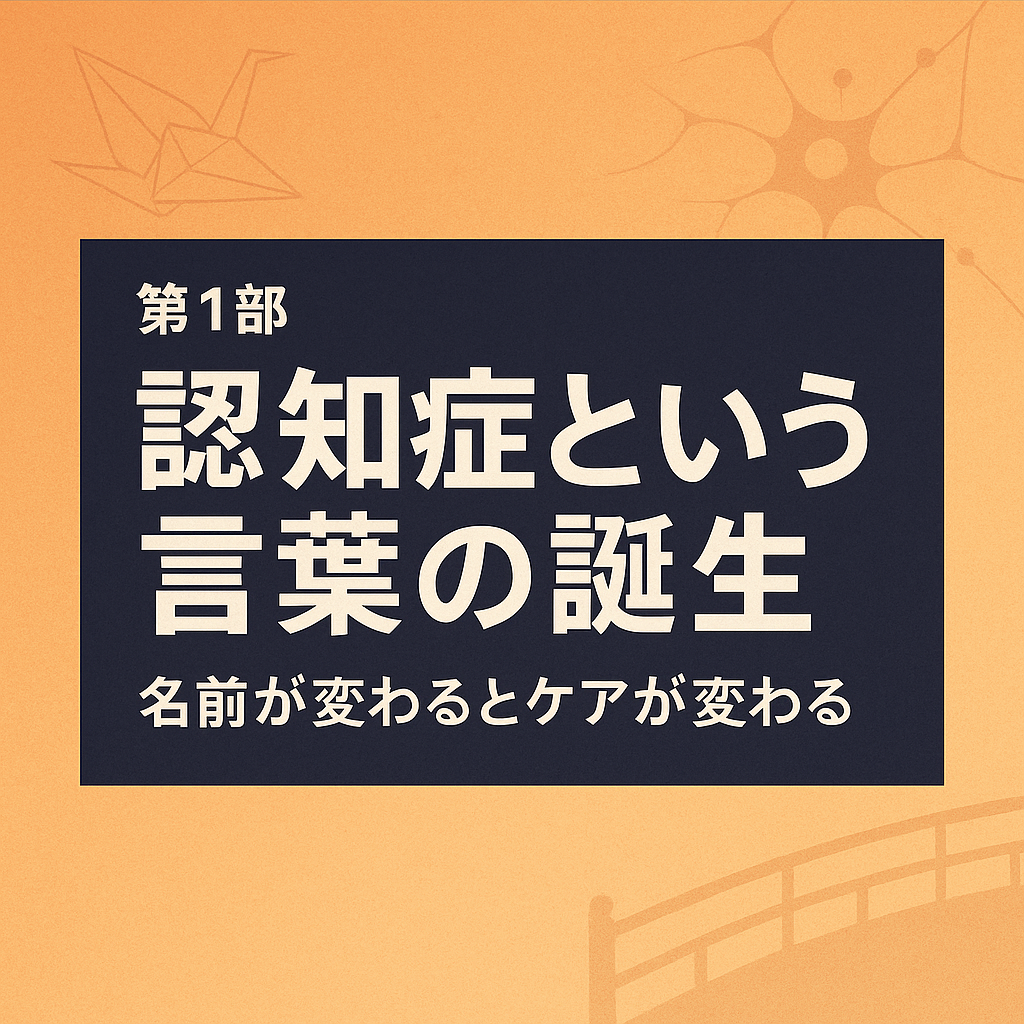
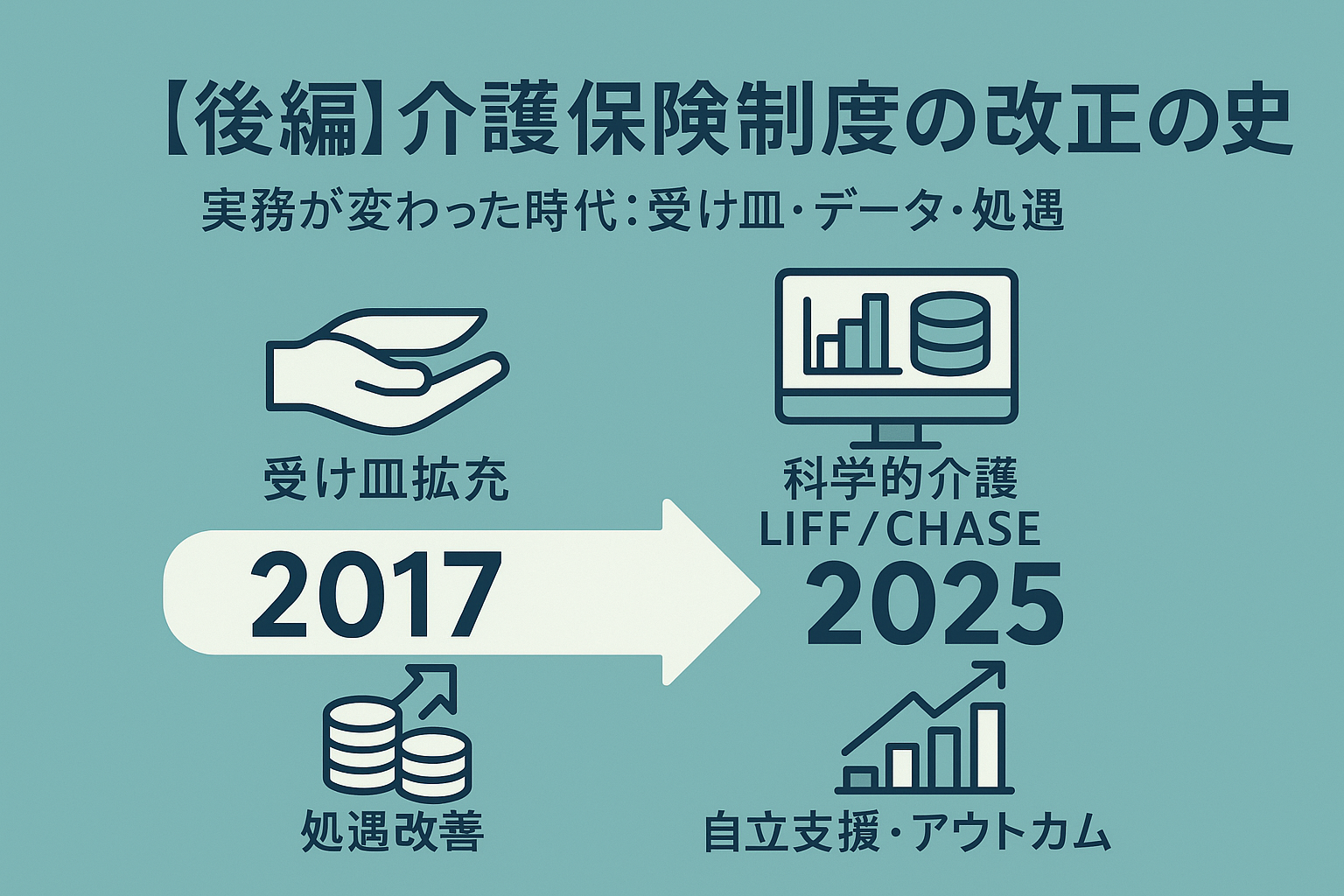
コメント