こんにちは、hiroです。
サービス提供責任者という役職を聞いたことありませんか?
ケアマネージャーの別の呼び方?
施設の責任者のこと?
など、私自身も疑問に思ったことでした。
今回は、サービス提供責任者について、じっくり解説致します。
この記事を読むことで、サービス提供責任者がどのようなものなのかが理解できますので、ぜひ、ご覧ください。
サービス提供責任者とは
サービス提供責任者(サ責)は、訪問介護事業所で利用者が適切な介護を受けられるよう、訪問介護計画の作成・実施調整・品質管理を担う専門職です。ケアマネジャーが作る全体のケアプランを、現場で実行できる形に落とし込み、ヘルパーが迷わず動ける体制を整えます。
主な役割
- 訪問介護計画書を作成・交付する
- 初回同行でアセスメントを行い、以後モニタリングする
- ヘルパーへ具体的援助方法を指示し、OJT・研修で技術を底上げする
- 家族・医療・ケアマネ等と連携し、サービス内容を調整する
- 記録の点検や請求前チェックを行い、加減算の漏れを防ぐ
- シフト・人員配置を調整し、当日の差し替えや緊急対応を采配する
- 事故・クレームの一次対応と再発防止策を周知する
~出典例:厚生労働省資料の「サービス提供責任者の業務」趣旨に基づき要約~
なるための主な資格要件
- 介護福祉士
- 実務者研修修了者
- 看護師・准看護師
- (経過措置)旧・介護職員基礎研修修了者/旧・訪問介護員1級修了者
※自治体の運用や経過措置で細部が異なる場合があります。最新の指定基準・通知を確認してください。
サービス提供責任者の仕事(詳説)
訪問介護計画書の作成・交付
- ケアマネの居宅サービス計画を受け、誰が・いつ・何を・どの手順で行うかを明文化。
- 変更が生じた場合は速やかに改訂・周知し、利用者へ交付する。
一言メモ・・・「入浴介助」なら、洗う順序、声かけ、立位前の停止秒数、介助者の立ち位置まで書く。誰が読んでも同じ行動になる粒度が基準。
初回同行・アセスメント・モニタリング
- 初回は原則同行し、生活歴・リスク・家族の希望を把握。
- 月次やイベント時に状態を見直し、計画・手順を更新。
一言メモ・・・生活動線、敷居、マットの端、家族の“してほしくないこと”をその場で言語化。以後のミスを先回りで潰す。
ヘルパーへの指示・研修・技術指導
- 手順書・連絡体制を整え、OJTやミニ研修で品質を平準化。
- 報告ルートを一本化し、インシデントは事実→評価→是正で処理。
一言メモ・・・指示は短く具体に。週15分×1回のマイクロ研修で「同じ失敗を全員で一度だけ」にする。
多職種・家族との連携
- サービス担当者会議に出席し、方針や役割分担を共有。
- 医療機関・地域資源との連絡線を維持し、調整を迅速化。
一言メモ・・・担当者会議は目的と役割分担を最初に合わせる。夜間の判断権限と連絡順を先に決めると不安が減るよ。
記録管理と請求前チェック
- 実績と記録の整合を確認。加算・減算の根拠を明確化。
- 監査を意識し、第三者が読んでも再現できる記録を徹底。
一言メモ・・・監査は日々の運用の積み重ね。事実→評価→次回指示で書き分け、加減算の根拠を残す。
シフト・人員配置調整
- スキル・移動時間・突発要因を踏まえて当日運行を最適化。
- 欠員発生時の差し替えや時間調整を即時判断。
一言メモ・・・欠員時は距離×スキルで再編。初動は「事実確認/応急・連絡/再発防止の提示」の三点セット。
事故・クレーム一次対応
- 初動三本柱:事実確認/応急・連絡/再発防止策の提示。
- 全体周知までを含めてワンセットで完了。
1日の流れ(モデル:住宅型有料の訪問対応を含む)
- 朝:連絡帳・ヒヤリ確認、当日差し替えの采配などを申し送りする。
- 日中:新規相談対応、初回同行、モニタリング、担当者会議、OJT/研修、計画・手順更新
- 夕方:請求前チェック、翌日以降のシフト確定、リスク共有
現場ケース
ケース1|物の定位置を崩して炎上
家族は「掃除ざっくりでOK」と言っていたが、本人は定位置が1センチ狂うと不安定になり、翌日問い合わせ殺到したケース。
対策:物の定位置を写真「B-02」で記録する。触れた場所を訪問後に1行メモする。基本、動かしたらもとに戻すを徹底する。
結果:クレーム0、作業+3分で安定した。
ケース2|入浴立位の転倒未遂
浴槽から立つ時に、縁だけを片手でつかむクセで、体が片側に寄りやすく、 立ち上がる瞬間に片足に体重が乗りすぎて、ぐらついた。
→ 結果、立位直後にふらつきや転倒未遂が起きやすい。
対策:立位前10秒停止する。両手すり把持、介助者は左斜め後方に待機。マットは壁から5cm内側固定する
結果:ヒヤリ月3件→0件。
ケース3|主観だらけの記録で差し戻し
「しっかり食べた」「元気そう」という記録をしたため、差し戻しになってしまった。
対策:
【事実】白飯150g完食、味噌汁150mlの半分。10:10入室、居間22℃。
【評価】咀嚼・嚥下問題なし。疲労感軽度。
【次回指示】水分200ml声かけ継続。マット位置は写真B-02参照。
結果:差し戻し0になった。請求前チェック時間も1/2へ。
訪問介護計画書の“粒度”見本(入浴ケースを抜粋)
- 脱衣所の敷居を跨ぐときは「右足からどうぞ」を添える。
- 洗浄は上肢→体幹→下肢。腹部手術痕は石けん不使用でぬるま湯。
- 立位前に10秒停止、介助者は左後方で支持。
- 退出前にマットを壁から5cmに戻す。写真B-02参照。
「安全に配慮」など抽象文は削る。センチと秒を書く。
向いている人(スキル感)
- 段取り力・交通整理力:複数案件を滞らせず回せる
- 文章力:計画書・手順書・記録を簡潔正確に書ける
- 交渉力:利用者・家族・ヘルパー・医療の利害を調整できる
- リスク感度:ヒヤリを事前に潰せる
ケアマネジャーとの違い
- ケアマネ(介護支援専門員):居宅介護支援事業所に所属。全体のケアプランを作成し、サービスを組み合わせる司令塔。
- サ責:訪問介護事業所に所属。ケアプランに基づき訪問介護計画書を作成し、現場を動かす監督役。
- ヘルパー:実際に介護を提供するプレイヤー。
両者とも「計画書」を扱うため混同されがちですが、計画の階層と所属が異なります。なお、現場ではケアマネ資格を持つ職員がサ責を兼務することもあります。
サ責を目指す人へ
要件を満たしていれば、実務は段取りと連携の型作りが勝負どころです。
≪最初の30日でやること≫
- 最初の1週目・・既存の計画・手順・連絡網の棚卸し。
- 2週目・・重点ケースに同行し、地雷リストと改善点を言語化する。
- 3週目以降・・ミニ研修を週1で回しながら、請求前チェックの型をチーム共通にする。仕組み化が進むほど、あなたは「火消し」ではなく「火を出にくくする人」になっていく。
まとめ
サービス提供責任者は訪問介護事業所に所属し、ケアマネではない。 ただし、事業所によってはケアマネ資格を持ってる人がサ責を兼務することもあるから、現場では境目が曖昧に見えることもあります。 サ責は、ヘルパーの働きやすさと利用者の安心の接着剤。誰かが雑にやると全部がバラけることも。逆に、筋の通った計画と連携を回し、そして確かな記録運用により事業所全体の満足度と生産性が上がる。地味に見えて、実は一番効くポジションです。
〇関連記事
✔ケアマネ不足は本当?現場の声と試験制度から見る最新事情
✔【これだけは知っておきたい】介護保険制度の超基本!申請から利用までの流れを徹底解説
〇noteを始めました!!
【お知らせ】noteを始めます。

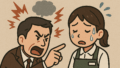
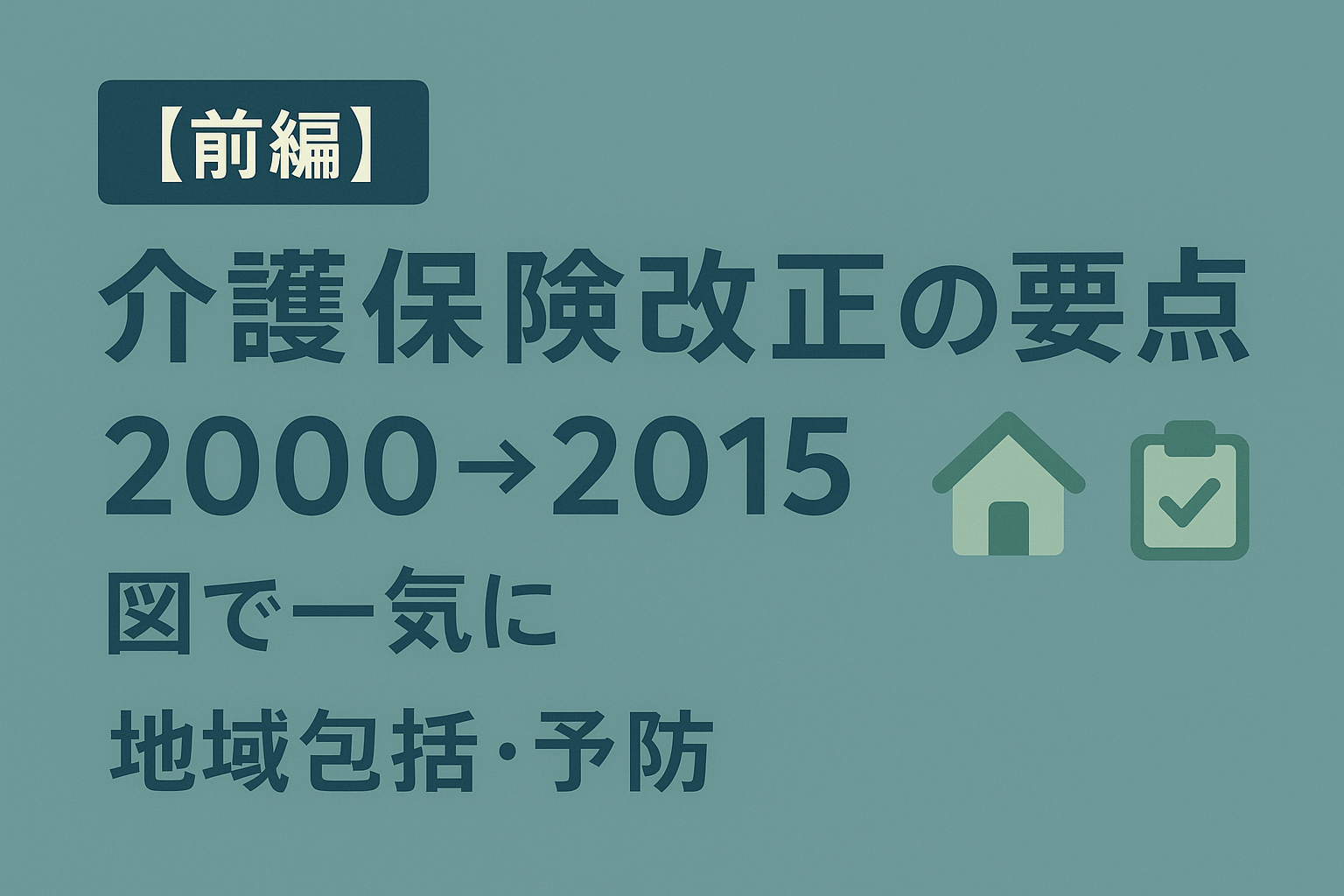
コメント