こんにちは、hiroです。
介護保険制度は2000年にスタートして以来、20年以上にわたって何度も見直されてきました。 「また制度が変わったの?」と感じる方も多いですが、理由は明確。前編では、2000年の開始から2015年の総合事業まで、要点だけを道標にして進みます。
今回は、介護保険制度の改正の歴史についてで
・介護保険の改正時に何が変わったのか?
・なぜ変わったのか?
・改正により、私たちにもたらす変化は?
などを解説致します。
なぜ介護保険制度は何度も改正されるのか?
介護保険制度がマイナーチェンジを繰り返す理由は、大きく次の3つです。
- ① 高齢者の増加による財政負担の拡大
→ 給付費が増えるため、自己負担や制度の見直しが必要になる。 - ② 介護人材不足への対応
→ 処遇改善加算などで人材確保を目指す。 - ③ 地域包括ケアへの移行
→ 施設中心から、住み慣れた地域での生活支援へシフト。
介護保険制度の主な改正内容【年表で理解】
| 年度 | 主な改正内容 | 背景・目的 |
|---|---|---|
| 2000年 | 介護保険制度スタート(措置から契約へ) | 高齢者介護の社会化。家族負担の軽減。 |
| 2003年 | 介護報酬改定、デイ・訪問介護の基準見直し | サービスの質確保と効率化。 |
| 2006年 | 介護予防重視へ転換。要支援1・2新設、地域支援事業創設。 | 重度化予防と医療費削減。 |
| 2009年 | 介護職員処遇改善交付金スタート。 | 人材流出対策。 |
| 2012年 | 処遇改善加算導入。在宅医療・介護連携強化。 | 地域包括ケアの基盤整備。 |
| 2015年 | 総合事業開始(介護予防給付の一部を市町村へ移行)。 | 地域主体の支援体制へ。 |
| 2018年 | 介護医療院創設、共生型サービス導入。 | 医療・介護の一体化。 |
| 2019年 | 特定処遇改善加算スタート。 | 経験・技能のある職員の賃上げ。 |
| 2021年 | 科学的介護(LIFE)導入、感染症対策強化。 | エビデンスに基づく介護へ。 |
| 2022年 | ベースアップ等支援加算導入。 | 物価上昇・人材確保への緊急対応。 |
| 2024年 | 介護DX推進、LIFE拡大、キャリアパスⅢ義務化。 | 科学的介護と生産性向上。 |
| 2025年(予定) | 医療・介護のさらなる一体化、地域包括ケアの完成へ。 | 団塊世代75歳以上到達に備える。 |
4つの時代で見る介護保険の変化
- 2000〜2005年: 制度の立ち上げ期。混乱と試行錯誤の時代。
- 2006〜2014年: 介護予防と地域支援への転換期。
- 2015〜2020年: 地域包括ケア・自治体主導の時代。
- 2021年以降: 科学的介護とデジタル化の時代へ。
2006年:予防重視型システムへの転換
2000年に介護保険がスタートしました。措置制度から、制度を選べる形にシフトし、その支払いも1割負担で利用できます。これが、いわゆる介護給付と言われています。
しかし、高齢者が増えるにつれ、国の財政が圧迫され、給付をしているだけでは財政が厳しくなってきました。
・地域支援事業の創設
給付事業とともに予防を重視する方針が打ち出された。
・施設へ入所の際、居住費と食費を保険給付対象外へ(自己負担に)
給付を介護サービスのみへ変更。低所得者には居住費と食費を抑える制度もあります。
・地域密着型サービスの創設
地域の方が利用できる一回り小さな介護施設です。施設だけでなく、通所などもあります。
・地域包括支援センタ―の創設
地域ごとに設置されていて介護の事ならなんでも相談に乗ってくれます。
・介護情報の公表
サービスの質の確保・向上が目的。介護業界も第3者目線を取り入れ、質を担保していく必要がある
・介護支援専門員資格の更新制度導入
介護支援専門員は介護サービスを使う上で大事な役割なので、研修を制度が開始されました。国家資格ではないのが不思議です。
2011年 介護サービスの基盤強化
地域包括ケアシステムの実現、持続可能な制度の実現に向けて
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設
字の通り、便利なサービス。国が在宅介護を推進しているのでニーズに合っている
・複合型サービスの創設
後に、看護多機能生活介護と名を変えていく
・介護予防・日常生活支援総合事業の創設
2014年
・介護予防訪問介護、介護予防通所介護を地域支援事業へ移行
要介護になる前から、人が介入する事ができるようになりました。
・特別養護老人ホームの入所要件を原則要介護3以上に
在宅で介護が必要な方は多いけど、要介護3以上の方を在宅で見るのは大変です。緊急性が高い方に優先的に入所していただくという方針です。
・一定以上の所得がある第一号被保険者の利用者負担を2割へ
一定以上の所得がある方と低所得の方とが同じ利用料だと不公平感がありますよね。累進課税みたいに所得に応じた額を支払う形へ変更。
前編はここまで。
前編は骨組みの理解がゴールです。次の後編では、2016年以降の「運用が変わった現場知」を具体化します。
介護保険制度の改正は手探りながら、利用者や介護者にとってはプラス要素が多くなってきています。後半は、介護職員への待遇についての内容もありますので、お楽しみに。
★関連記事★
✔【これだけは知っておきたい】介護保険制度の超基本!申請から利用までの流れを徹底解説
✔昔と今でどう変わった?特養での医療対応と受診付き添いの実態
✔介護の処遇改善手当、知ってる?「交付」から「加算」へ変わった本当の理由
★noteを始めました★
【お知らせ】noteを始めます。
★『おはよう21』は1冊から購入できますが、定期購読がおすすめです。
・継続的に学びが積み重なり、スキルアップにつながる『おはよう21』
・バックナンバーのデジタル版が見放題
・最新号が毎月届くので買い忘れなし
➡公式サイトはこちら
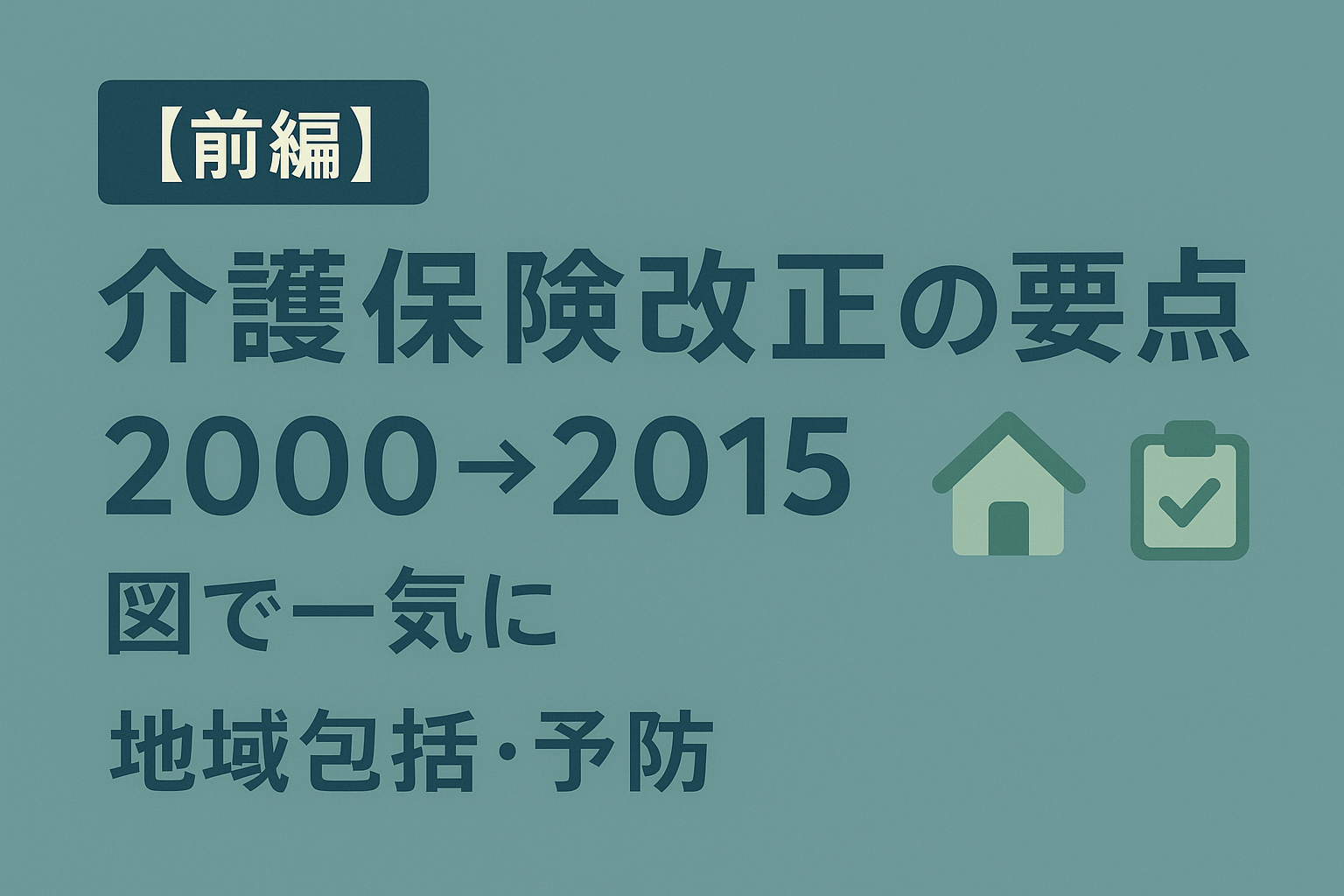

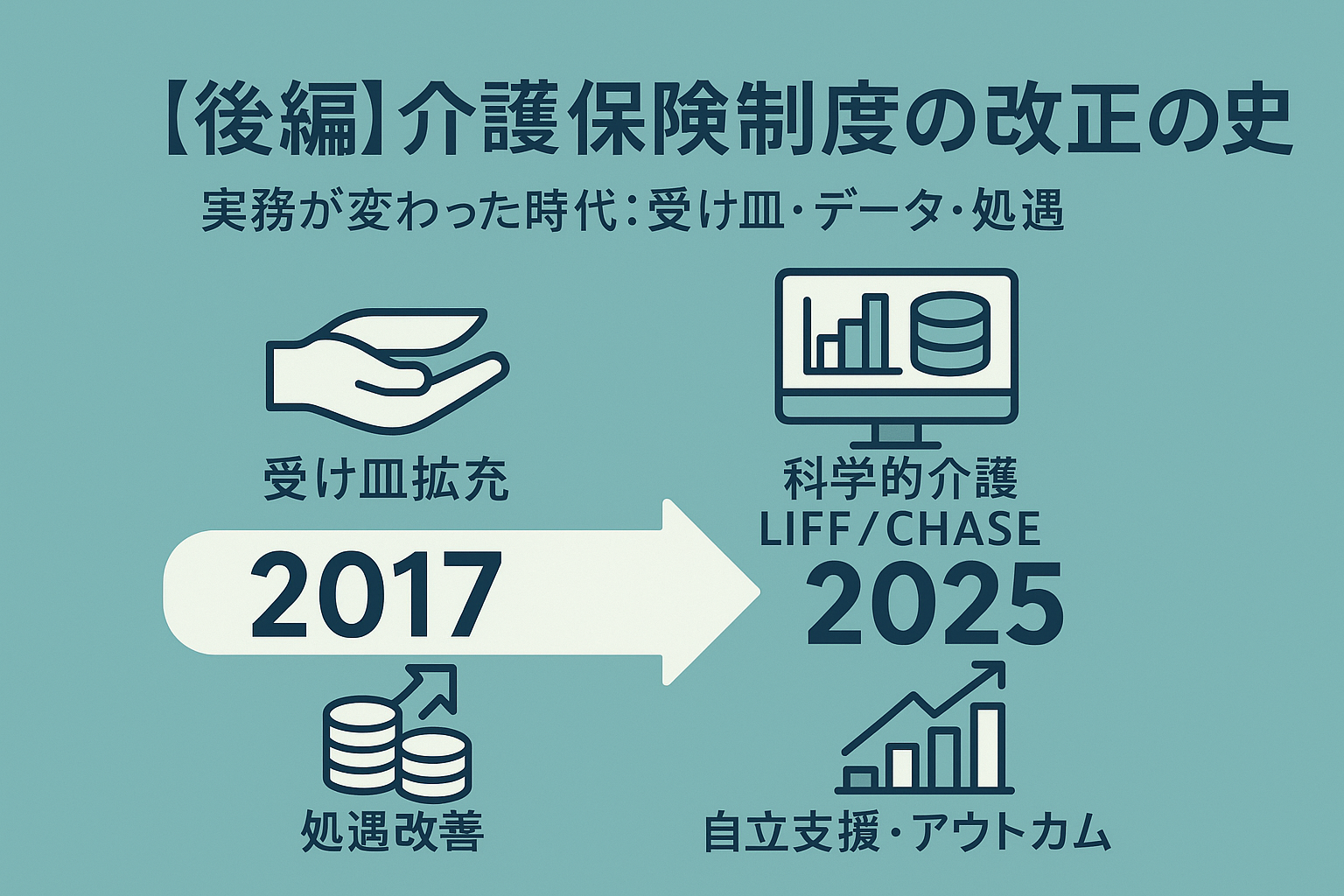
コメント