こんにちは、hiroです。
私は、介護職を18年間続けており、現在も特別養護老人ホームで働いています。長い介護経験から不安を抱いたことや対処方法、また新しく介護を始める方へ何か伝えることはないか?何か役に立つことはないか?と思ったことからこのブログを運営しております。
介護職として不安を抱いたことと言えば、介護職の給与です。
私も悩んだ時期がありました。しかし、給料を上げる方法がある事を知り、今は安心して介護職をしています。
今回はそのような「介護職のリアル=待遇、つまり給料」についてお伝えしていきます。
同僚が辞める理由は「給料が低いから」
つい先日、同僚からこんな相談を受けました。
「給料が低くて生活が厳しい。今月で辞めようと思うけど、手続きはどうすればいい?」
普段そんな様子を見せていなかっただけに驚きましたが、これこそ介護職の現実だと痛感しました。
介護職の給料の内訳と実情
同僚は夜勤を5回こなして、手取りはおよそ24万円。介護職としては平均的ですが、生活するには厳しい額です。
私の施設の場合、給与の内訳は以下の通りです。
- 基本給
- 処遇改善手当
- 住宅手当・家族手当
- 夜勤手当
- 残業手当
かつては残業が多く、残業代でなんとか収入を補えていました。しかし職員が増えて残業も夜勤も減り、結果的に給与が激減。これが退職の大きな理由になりました。
介護職と一般企業の年収差
厚生労働省の「介護従事者処遇状況等調査」では、介護職の給与は少しずつ上がっています。昨年度より月1万円ほど増加しました。
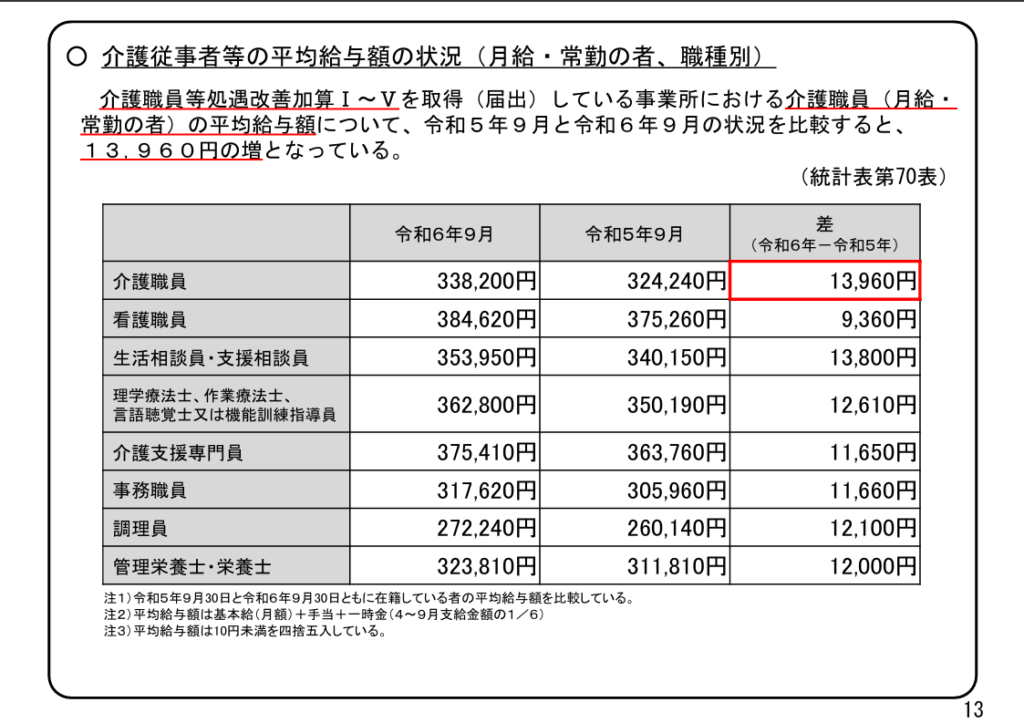
【厚生労働省ホームページ「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」から抜粋】
一方で、国税庁の統計によると2024年の民間給与所得者の平均年収は 478万円。
介護職と比べると 100万円以上の差 があります。
「介護職は低賃金」「将来が不安」という声が絶えないのも当然です。
有料老人ホームと特養、どちらが高い?
私自身、有料老人ホームで働いた経験もあります。給与は特養より高めでしたが、その分「お客様」としての要望に応えるプレッシャーも強く、職員への要求も厳しかった印象があります。
待遇が良い分、責任や精神的負担も大きい。どちらが良いかは一概には言えません。
給料を増やすための選択肢
介護職で収入を増やす方法はいくつかあります。
- 資格取得
- 昇進・昇格
- 有料老人ホームなど営利企業で働く
- ダブルワーク
ただし資格試験は年1回で勉強時間も必要、昇進すれば責任が増して心身の負担も大きくなります。
介護職の賃金は上がってきているのは事実ですが、一般的にみると低い水準のままです。
何故なら、収入の大部分を介護保険に頼っている為、上限が限られているからです。追い打ちをかけるように、昨今、物価上昇のスピードが速く、給与が上がっても余裕を感じられないというのが現実です。
そこで私が勧めたいのが 副業 です。
副業で広がる可能性
私はこれまで以下の副業を経験してきました。
- メルカリ出品 → 営業力・値付けの感覚
- 動画編集 → 企画力・編集スキル
- チラシ作成 → デザイン・配色の知識
- プログラミング → AIやデジタル活用の理解
意外な場面で役立つこともあり、施設イベントのチラシを作った際には「プロみたい」と職員や家族から褒められました。
副業のメリットは、収入だけでなく 自分のスキルが成長すること。それが本業に活きたり、転職の武器になったりします。
まとめ|「給料が低いから辞めたい」にどう向き合うか
介護職の給与水準が低い現実はすぐには変わりません。
私の同僚は派遣に戻る決断をしましたが、同じ悩みにぶつかる可能性もあります。
だからこそ、これからは 「どうやって自分の武器を増やすか」 が大切です。
会社に頼るだけでなく、副業やスキル習得で収入の柱を増やすことが、将来の安心につながります。
あなたはこの現実を、どう乗り越えますか?
〇関連記事
✔【お金の話】今さら聞けない介護のお金にまつわる話を解説~介護職の給与アップ方法は?平均給与は?介護サービスの定価は?~
✔介護の求人状況を解説。~自分にあった働き方の見つけ方~
✔介護の処遇改善手当、知ってる?「交付」から「加算」へ変わった本当の理由定期購読はこちら
〇介護情報誌『おはよう21』
~1冊から購入できますが、定期購読がおすすめです~
- バックナンバーのデジタル版が見放題
- 最新号が毎月届くので買い忘れなし
- 継続的に学びが積み重なり、スキルアップにつながる
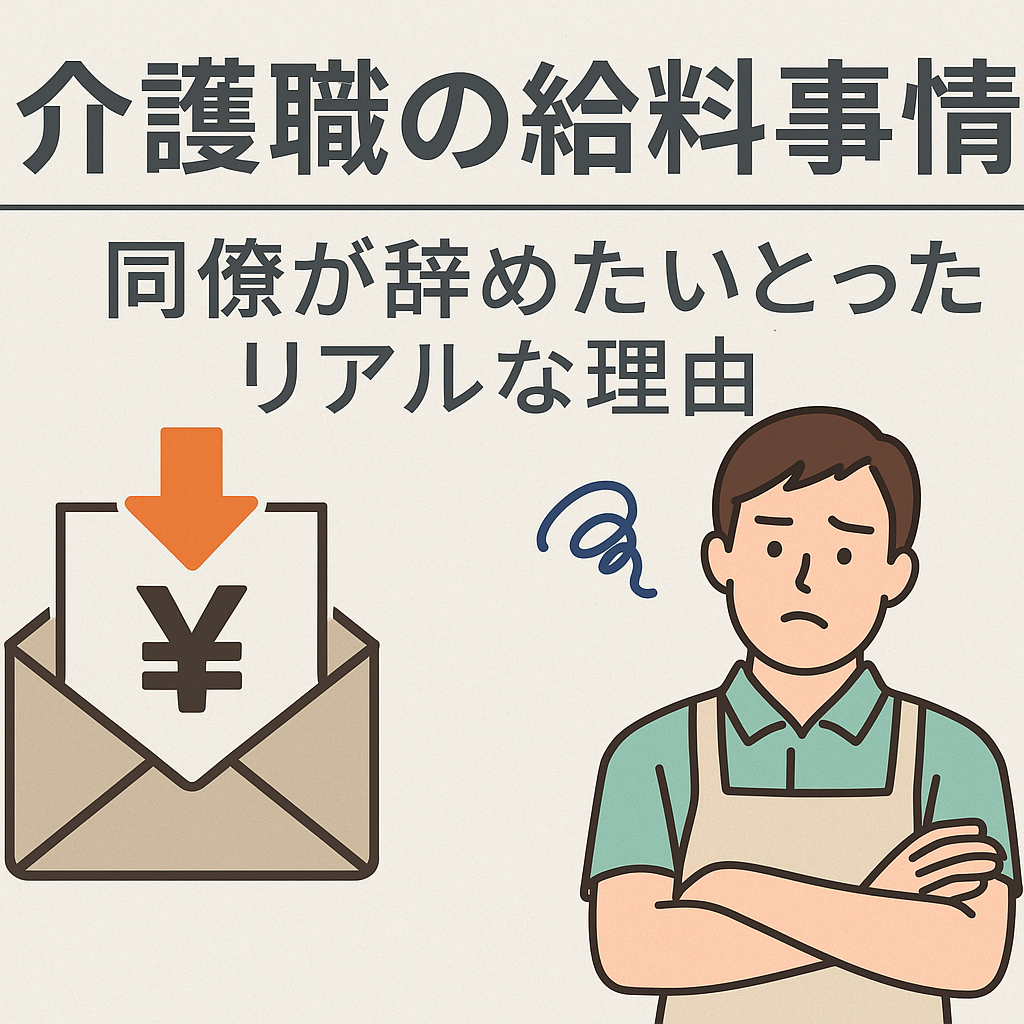

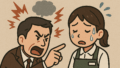
コメント