介護疲れという現実
こんにちは、hiroです。
「介護疲れ」という言葉を耳にしたことはありますか?
自分では気づかないうちに、心も体も限界に近づいている——。
そんな状況に陥る介護者は、決して少なくありません。
私は介護職を18年間続けています。日々の現場を通して強く感じるのは、
「家での介護は想像以上に大変」ということです。
実際に私は、身内や家族を介護した経験はありません。だからこそ、在宅介護をされている方がどれほど大きな犠牲を払っているか、どれほど「辞めたくても辞められない」状況にあるのかは、想像するだけでも胸が苦しくなります。
それでも、プロとして人を介護している立場だからこそわかる「介護の大変さ」があります。ここでは、特に大きな負担になりやすい点をいくつか紹介します。
在宅介護で大変なこと
1. 排泄介助
排泄は介護の中でも特に負担が大きい部分です。尿ならまだしも、便の処理は誰にとっても精神的に苦痛を伴います。
施設であればタオルやバケツ、陰部洗浄用の物品が揃い、汚れた衣類も洗濯に回せます。しかし在宅介護では、処理や後片付けを家族が担うことになり、尿や便で部屋が汚れるだけで大惨事になりかねません。だから、介護者は疲れてしまうのです。
2. 夜間の介護
高齢者は夜間にトイレが近くなることが多いです。施設なら夜勤職員が対応しますが、自宅では家族が起きてトイレへ連れて行ったりオムツ交換をしたりしなければなりません。これが続くと、介護者自身が深刻な睡眠不足に陥ってしまいます。
3. 認知症の対応
認知症の方を介護する場合、大変さは一気に増します。
認知症の行動障害の中でも徘徊は大きな課題です。一瞬の隙に外へ出てしまうと、自力で帰宅できないこともあり、転倒や大きなトラブルにつながります。常に目を離せない状態は、介護者の心身を大きく消耗させます。
このように挙げればきりがありません。実際に特養へ入所を希望されるご家族の多くが、「一日でも早く施設に入れたい」と口にされるのは、それほど在宅介護が厳しい現実を物語っているからです。
介護疲れとは?
冒頭でも触れましたが、近年、「介護疲れ」という言葉をよく耳にするようになりました。
介護疲れとは、長期間にわたる介護によって心身が疲弊し、介護を続ける力や意欲が低下してしまう状態を指します。
厚労省調査の調査によると、在宅で介護をしている方の多くが疲労感や孤独感を抱えています。特に老老介護や介護離職など、支える側にも負担が集中するケースでは深刻になりやすいのが現実です。
介護疲れの原因
- 身体的疲労:夜間の対応、排泄や移乗などの体力的負担
- 精神的疲労:感情のすれ違い、孤独感、先の見えない不安
- 経済的負担:介護離職、収入の減少
- 情報不足:制度やサービスを知らずに抱え込んでしまう
介護疲れのサイン
次のようなサインが続いている方は要注意です。
- イライラが止まらない
- 寝つきが悪い、体調不良が続く
- 趣味や外出に関心がなくなる
- 「自分が倒れた方が楽だ」と思うことがある
少しでも当てはまる場合は、早めに対策を取ることが大切です。
介護疲れを軽減する方法
私が18年の介護現場で学んだことは、介護は「頑張るもの」ではありません。介護現場でも、頑張りすぎると逆にうまくいかない場面を何度も目にしてきました。
例えば、認知症の方が入浴を嫌がるとき。必死に説得しても逆効果になることがあります。そんな時は、頑張らずに時間を変える、人を変えることでスムーズにいくことも多いのです。
在宅介護も同じです。頑張りすぎると介護者の心が折れてしまいます。だからこそ、介護サービスを積極的に活用してください。
- デイサービスやショートステイ(レスパイトケア)
- 夜間訪問による排泄や見守りサービス
- 通い・泊まり・訪問が一体化した小規模多機能サービス
- 家族・友人に気持ちを話すこと
- 専門職(ケアマネ、地域包括支援センター)への相談
体験談:父娘の介護
ある父子家庭で、娘さんが父親を懸命に介護していました。最初は父も感謝を伝えていましたが、やがて「やってもらうのが当たり前」になり、不満を口にするようになったのです。父の感謝が“当たり前”に変わった瞬間、娘の心は折れ始めました。
娘さんは友達との時間や自分の人生を犠牲にして介護を続けましたが、やがて関係が悪化してしまいました。父親が施設に入所した後、娘さんはようやく自分の人生を取り戻したそうです。
「ありがたい」が「当たり前」に変わるのは、誰にでも起こりうることです。だからこそ、人に頼ることが必要なのです。
介護疲れを放置するとどうなるか?
介護疲れを放置すると、次のようなリスクがあります。
- 介護うつ
- 介護放棄・虐待
- 介護者自身の健康悪化
最も避けなければならないのは、老老介護の末に心中してしまうケースです。実際に私の施設の近隣でもそうした事件がありました。
介護者が健康で心に余裕を持ってこそ、良い介護は続けられます。
まとめ:介護は一人で抱え込まないで
在宅介護をされている方へ。
最後に、もし少しでも悩んでいるなら…どうか「介護を頑張りすぎないでください」。
頼ることは悪いことではありません。むしろ、介護を続けるためには必要不可欠です。
まずは、市町村の役所や地域包括支援センターに相談してみましょう。
それが「一人で抱えない介護」への第一歩です。
介護保険の申請に費用はかかりませんし、あなたの状況に合った支援策を一緒に考えてくれます。
介護は、一人で背負うものではありません。
あなた自身を大切にすることが、結果的に家族にとっても最良の介護につながります。
〇関連記事
✔介護職のストレスで心が折れそうな時に試してほしい5つの対処法
✔介護の新しい3Kとは?|感謝・工夫・健康でポジティブに働く
✔もう我慢しない。介護職員を守るカスハラ対策と新法のポイント | 介護しよ.net
〇介護情報誌『おはよう21』~1冊から購入できますが、定期購読がおすすめです~
- 最新号が毎月届くので買い忘れなし
- 継続的に学びが積み重なり、スキルアップにつながる
〇 noteを始めました。
こちらでは介護に留まらず、私が普段思う事や、趣味など自由な内容を記事にしていきますので、
こちらから!👉hiro|note

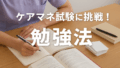

コメント