こんにちは。
hiroです。
今回は、本題に入る前に最近,
「介護って、奥深いな」
と思ったことがあり、共有したいと思います。
それは、ベテラン職員が、ある利用者に対しての対応方法を見ての事です。
仮にA職員とします。
そのA職員の介護は決して丁寧とは言えない介護職員でした。
乱暴ではないがケアが少し雑な所があったり、利用者に対しての声掛けも、ちょっとぶっきらぼうだったりという状態。
しかし、なぜか利用者にも他の職員にも好かれていました。
他の職員にその方の事を聞いたり、観察していると、ある事を気づきました。
それは、不器用ながらも相手に配慮を持っている、事でした。
わかりやすい例を挙げると、
風呂介助の時。
私は衣服介助をしていて、A職員は体を洗ったり浴槽にご案内する担当でした。
そのうち、中から
「寒いから今日は(入浴は)長めにしよう」や「風呂どうよ?」など、話し声が聞こえ、常に笑い声が聞かれていました。
また、食事介助の時、自分を含めて、中々食べさせられない利用者に対して、声掛けとスプーンの使い方で全量近く食べさせたり、と言う具合。
これを聞いて、
何がすごいの?
当たり前の事じゃん?
と思う方もいると思いますが、私はいくつかの施設を経験していますが、当たり前が出来ているところが少なかったので、とても素晴らしいことだと思います。
もし、上記の事を当たり前と感じるあなたはプロの介護士なのかもしれません。
介護職にとって、配慮を持つ事はとても重要です。
そして、相手を笑顔を引き出せることは、素晴らしい技術だと感じます
声掛けや食事介助一つとっても、「技」があります。
介護職は、経験が長ければよい介護士とは言えない業種であるので、普段の業務をしながら自分で考え「技」を磨いていくことが大切です。
今回のテーマは「介護職にとって必要な3つの事」となりますので、テーマにぴったりなエピソードだと思いましたので、ご紹介しました。
さて、本題に入りますが、今回は『介護職にとって必要な3つの事』というテーマです。介護は簡単にみえますが、そうではない場面もあります。大切なことを3つに絞ってみましたので、共有したいと思います。
【1】継続的な学習が大切
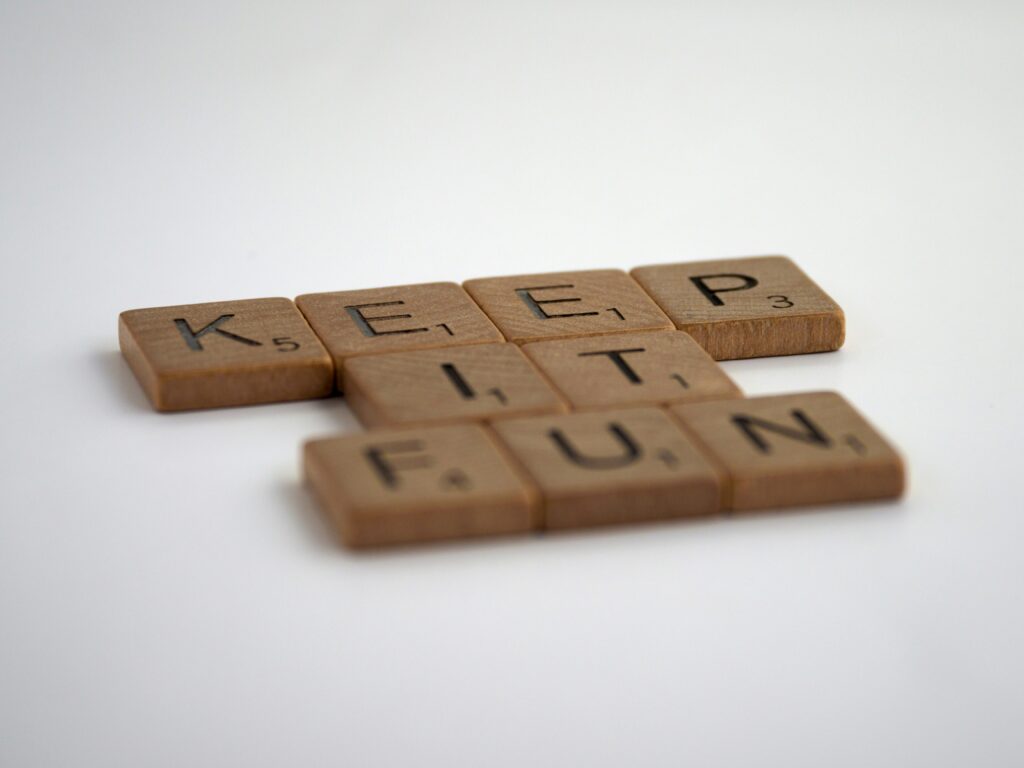
継続的に学習することは、どの職業についていても必ず求められてきます。
学習が大事、と言われて、机に何時間も向かう事を想像する方もいると思います。資格の勉強や、将来に向けて何かを勉強する方はそうかなと思いますが、私の言う、学習、は少し違っています。
それは何かというと、一日一つからでよいので、
「毎日、疑問を持ちそれについて調べること」 です。
例えば、
一、褥瘡って何?と聞かれて、しっかり答えられなかったので確認する。
二、内出血と皮下出血は同じじゃないの?と聞かれて答えられなかったので確認する。 など。
なんでも良いので、ある言葉を耳にしたり、状況をみてわからない事、説明できない事があったら調
べることを継続的にやること。一日1つでもよいと思います。
また、毎日当たり前にやっている食事介助、排泄介助、入浴介助などを改めて、やり方を調べてみる
のも新しい発見があったりしてとても勉強になります。
何事も基本を深く、深く極めることであらゆる場面で対応ができるようになると思います。
介護は誰でもできる仕事だと思いますが、学習と経験が必要になります。学ぶことは利用者様の命を
救うことにも通じると思います。
介護業界は経験年数が長いからと言って対応力や知識があるとは言えない業界だと思います。経験相
応の方とそうではない方の違いは、学習しているかしていないかだと思います。
最近、私は介護の経験貯金でやっていた時期があり、自分の対応力の無さや勉強
不足でとてもみじめな思いをしたことがありました。
今でもわからないことだらけで、毎日反省の日々ですが、
毎日最低一つ気になることを調べる事は継続しています。
あと、調べることで介護がさらに面白く感じてくる場面があるかもしれませんのでお勧めです。
【2】介護はサービス業である

何、当たり前の事を言っているんだ?
と思った方もいるかもしれませんが意外と、認識が違う方も多いのが介護業界だと思っています。
サービス業と聞いてどの職業を想像しますか?
アパレル店員、理容師、美容師、ホテルマンなど、たくさんありますが、介護職も立派なサービ
ス業と言う事が総務省が示している「日本標準産業分類」の中で分類されています
『総務省が示している「日本標準産業分類」では、 介護の業種は「P 医療,福祉」の「85 社会保険
・社会福祉・介護事業」に分類されています 。「P 医療,福祉」は、「L 学術研究,専門・技術サ
ービス業」から「R サービス業(他に分類されないもの)」までの間に入ることから分かる通り、日
本標準産業分類ではサービス業に分類されます。』
ひと昔の介護は
措置制度といって、行政がサービス内容を決めるような仕組みで、誰に対しても同じサービスが提
供された時代がありました。
そういう中、措置制度に対して、
・サービス内容や時間が、利用者の希望に沿わない場合もある
・サービスの質が低いと感じても、事業者を変更することが容易ではない
などという声が取り上げられ、
2000年 選択と契約の下に介護保険制度が施工されました。
介護保険制度は、利用者一人ひとりのニーズに合わせたサービス提供を促進するという方針です。
・接遇スキルを身につける
相手が認知症の方であっても、言葉遣いや表情、身だしなみが大切です。丁寧な言葉遣いや優しい表情は、利用者に伝わります。
例えば、
・不適切な言葉遣い
・利用者様を無視する
・上から目線
・職員中心のケア
などが現場職員では見られます。
過去に私は5か所以上の介護施設を見てきましたが上記の認識がズレている職員が必ず数人いました。
今は、認知症の方を馬鹿にした行動や言動や、雑な対応は不適切ケアと呼ばれてしまいます。
職員も人間ですので、イラッとすることもあるのでしょう。
そういう場合は、他の方に変わってもらう方がうまくいくことが多いです。
利用者さんのことを考え、相手を不快にさせない事を意識し、利用者さんそれぞれの状態やニーズに合わせた介護サービスの提供する事が、安心感を与えるでしょう。
【3】気づきを持つ・気づいてあげる

こちらは現場にいて一番意識して欲しいことです。
具体的には
≪整容≫
・髪の毛は整っているか?
・目ヤニはついていないか?
・衣服は適切か?(冬場に脛が出ていたり、よれよれの服を着ていたり)
≪変化≫・・いつもとは違わないか?
など、ほんと小さなことで良いですので気づきを持ちたいですね。
私の経験談ですが、昔、利用者さんが脳梗塞を起こしている事を発見したことがありました。
その方は、両腕に強い拘縮がある方で、無理に腕を動かすと骨折してしまいそうなくらいで、更衣介助は一苦労でした。
しかし、ある時、居室から食堂へ誘導するために衣服を直していた時、拘縮の固さを感じずに服を直せました。
「あれ?」
と違和感を感じ、看護師へ報告し、受診した所、脳梗塞でした。
何かいつもと違うかなと感じたら
小さな変化こそ相談・報告することが大切と思います。
利用者様が施設に入所している間、一緒に過ごす時間が長いのは介護職です。
特に、認知症の方や言語障害で自分から訴えができない方もいらっしゃいます。
そういう方には家族の代わりに、小さな変化に気づいてあげられる介護職でありたいですよね。
【まとめ】
今回は、「介護職にとって大切な3つの事」として共有させてもらいました。
【1】継続的な学習が大切
【2】介護はサービス業である
【3】気づきを持つ・気づいてあげる
上記の【1】、【3】については、介護職に限ったことではなく、どの職業だとしても必要な事と思います。
なにも難しいことではないですが、実行するとなると一気にハードルが高くなる気がします。
そういう時は、小さく始めることが秘訣ですね。
今回も最後までご覧いただいてありがとうございます。
また次回をお楽しみに!



コメント