こんにちは、hiroです。
2000年に介護保険制度が開始されましたが、介護は「保険給付」だけじゃ足りない、要介護にならないような取り組みも必要だ、という流れから、その6年後の2006年、地域全体で暮らしを支える仕組みとして地域支援事業が開始されました。
地域支援事業は、様々な事業から成り立っていますが、今回は、地域支援事業の全体像を解説致します。
地域支援事業とは(定義と目的)
- 定義:市町村が実施する、介護予防と生活支援、権利擁護、連携強化など「地域まるごと支援」のパッケージ。
- 目的:要介護化の予防、暮らしの継続、医療介護連携、地域づくり。
- 保険者:市町村。評価・計画は「介護保険事業計画」に紐づく。
地域支援事業は、2006年に介護予防を生活に取り入れる事で要介護にならないように運動などを取り組み。また、要介護、要支援になっても住み慣れた地域で生活し続けることができるような仕組みづくりを目指し、開始されました。地域支援事業の開始理由には、もう一つの理由があります。2000年に介護保険制度が開始され、給付事業が開始されました。しかし、介護保険制度では、サービスは原則1割負担からスタートしていて、介護保険施設の居住費、食費も保険内で支払われていました。その為、財政が圧迫され、健康寿命を長くする意味もあったのです。
全体像マップ(図解の言語化)
- 中央:地域支援事業
- 周囲に4ブロック
- 介護予防・生活支援サービス事業(総合事業)
- 一般介護予防事業
- 包括的支援事業
- 任意事業
- 矢印:地域包括支援センターをハブに、住民組織・医療機関・事業所・自治会・ボランティアへ双方向。
4つの柱と主なメニュー
介護予防・生活支援サービス事業(総合事業)
- 対象:要支援1・2と「基本チェックリスト等で把握した事業対象者」。
- ねらい:フレイル予防、社会参加、軽度者の自立支援
訪問型サービス
- 従前相当の訪問介護
従来の要支援向け訪問介護に相当。生活援助・一部身体介護など。 - 訪問型A(基準緩和)
地域の人材活用を前提に、生活支援中心。調理・掃除・買物同行など。
例)短時間・定型化された生活援助を効率的に提供。 - 訪問型B(住民主体)
ボランティア・NPO等が担う見守り、買物・外出支援、軽微な家事の手助け。
例)週1回の見守り訪問とゴミ出しサポート。 - 訪問型C(短期集中の専門職)
理学療法士や保健師等による評価とプログラムで、数週間〜数か月の集中的介入。
例)転倒予防の個別プログラム、服薬管理の整理。 - 訪問型D(移動支援等の整理枠)
生活圏内の外出支援を柔軟に設計(地域の交通資源との連携がカギ)。
通所型サービス
- 従前相当の通所に加え、基準緩和の通所を実装。運動・口腔・栄養などを組み合わせ、社会参加の再開を後押し。地域リハ・歯科・栄養の専門職が関わりやすい設計が推奨。
一般介護予防(通いの場づくり等)
住民主体のサロン、体操教室、栄養講話、口腔機能向上、更に協議体の運営やコーディネーター配置で、地域資源を増やしつなぐ基盤整備を行う領域。
介護予防・日常生活支援総合事業(いわゆる“総合事業”)は、要支援1・2やそれに準じる「事業対象者」を、市町村主導で“地域の力”も使って支える仕組み。目的は自立支援と重度化予防、そして介護保険の持続可能性。全国一律でガチガチに縛るより、地域の実情に合わせて柔らかく設計できるのがミソ。
一般介護予防事業
一般介護予防事業は、要介護の認定有無に関わらず主に65歳以上の地域住民全般が対象。フレイル予防を軸に、運動・栄養・口腔・社会参加の4本柱で「地域で元気に暮らし続ける」を支える、市町村主導の取り組みです。要支援者向けのサービス提供(訪問型・通所型)を扱う「介護予防・日常生活支援総合事業」と並ぶもう一つの柱で“通いの場”の創出・拡大と、住民主体の支え合いを育てるのが役割です。
普及啓発・アウトリーチ
- フレイルやフレイルサイクル(低栄養→筋力低下→活動減)の啓発
- 地域イベント、商業施設、病院外来、薬局と連携した出前講座
- 体組成・握力・歩行速度・口腔チェック等の簡易スクリーニング
通いの場(住民主体サロン等)の創出・拡大
- 体操、ミニ講話、交流、買物支援の組み合わせ
- 会場は公民館・自治会館・商業施設のイベントスペースなど
- 週1〜月2回の定期性、1回60〜90分が目安
コーディネーター配置・協議体運営
- 地域の点在資源を「線」にし、重複や空白を埋める調整役
- 行政、包括、専門職、住民代表、事業者で地域ケア会議/協議体を持ち、評価と改善を回す
専門職の関与(ハイブリッド支援)
- 理学療法士、歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、保健師などが初期設計と定期モニタリングで関与
- 住民運営を核に、必要場面だけ専門職がスパイス投入の設計に
ボランティア育成・人材循環
- ファシリテーター、体操リーダー、見守り係、記録係の役割分担
- 年2回の養成・更新研修、活動保険・交通費の取り扱い整理
一般介護予防事業は、“通いの場”を核に人と人の回路を復活させ、運動・栄養・口腔・社会参加を地続きにする取り組みです。専門職が設計で支え、住民が主体で回す。結果として、閉じこもりの減少、フレイル進行の抑制、支え合いの再生が起きます。地域の実情に合わせて、無理なく始め、続けられる形に磨き込む。これが成功の最短ルートです。
近隣のショッピングモールに行くと、イベントスペースに人が集まっており、よく見ると高齢者が映像に合わせて体操をしていました。店舗が”通いの場”を提供し、高齢者の方がそこで体操に参加をする。体操終了後は、コーヒーの一杯でも飲んで帰る方もいらっしゃると思います。まさに”三方良し”の構造が出来ていますね。
★参考
✔総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)|厚生労働省,これからの地域づくり戦略ー集い・互い・知恵を出し合い3部作ー
✔(介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン案(骨子)
✔地域支援事業実施要綱及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインの一部改正について
★関連記事
✐【これだけは知っておきたい】介護保険制度の超基本!申請から利用までの流れを徹底解説 | 介護しよ.blog
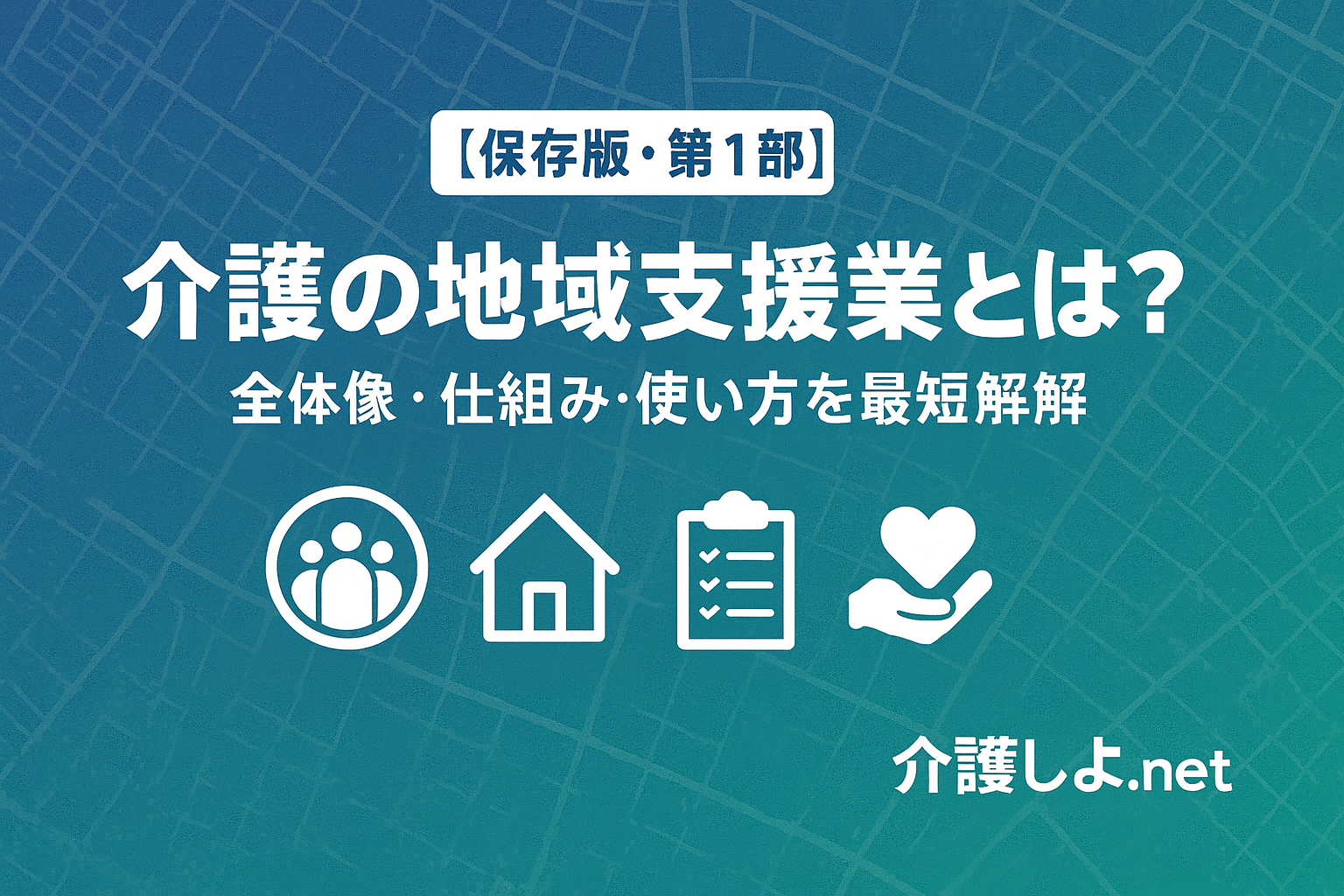
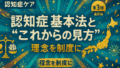
コメント