こんにちは、hiroです。

hiroプロフィールを編集
今週も最新の介護Newsです。
ケアマネ資格「更新制」廃止を厚労省が部会に提案へ
更新研修を修了しないと資格が更新できない現行ルールをやめ、定期的な研修は続けつつ縛りは緩める方向。
現場的な意味: 研修日程に振り回されにくくなり、利用者対応や記録の時間を確保しやすい。事業所側は計画的な研修支援体制を整える必要。
≪解説≫
ケアマネージャーは、国家資格ではなく、民間資格でもない。介護保険法に基づく公的資格(都道府県知事の登録)である。ケアマネになる為には、実務経験(5年以上)を満たしたうえで介護支援専門員実務研修受講試験に合格→実務研修を修了→都道府県知事に登録して介護支援専門員証の交付。全国共通の仕組みだが、手続き主体は都道府県。
正式名称は「介護支援専門員」というが、世間ではケアマネ(ケアマネジャー)と呼ぶ。
試験に合格した後、研修を受けてからの実務という流れになっていて、合格してからも実務までが長い。研修や資質向上事業など、登録後も更新・研修が求められ、研修には、金銭面と時間の負担が大きい。その為、試験に合格するが、潜在ケアマネ、も多数いると言われている。ある地域では、20代のケアマネが0名であったことが問題となっており、若手のケアマネの育成も課題となっている。そんな中、更新制度の廃止はケアマネの負担軽減につながり、ケアマネ不足解消の一手となるかもしれない。また、実務経験年数も3年という案も出ているという。
記事はコチラ👉介護ニュースJoint
「介護デジタル中核人材」研修が増設へ(応募殺到で追加)
厚労省の生産性向上プログラム。定員満了につき研修セット増設のお知らせ。参加状況はダッシュボードで公開。
現場的な意味: ICT導入の旗振り役を内部育成するチャンスが一段増。法人は対象者の選定と勤務扱いの取決めを急げ。
≪解説≫
厚生労働省が、令和7年度 デジタル中核人材養成研修を募集していました。
要項に
『本研修は、現場で課題を見出し、改善策を立案・実践する力を持つ「中核人材」を育成することを目的としています。介護の質を高める倫理観やチームでの実践力、リーダーシップを身につけ、職員の働きやすい環境づくりや利用者の自立支援の実現をめざします。』と記載されています。
介護業界の将来を見据えて、リーダーシップを育成する研修となり、業務の効率化やICT化、そして化学的な介護の推進を担える力も求められます。
介護業界は、変化に弱い業界だと、身をもって感じます。現場単位だと、中々本格的な研修というのは難しく、国が用意してくれた形です。
今回は募集に応募が殺到し、締め切り日を延長するという内容です。しかし、一部の地域では募集人員に満たないところもある為、その地域には個別に連絡していくと書かれています。
記事はコチラ👉WAM+1
福祉用具の「全国平均貸与価格・上限」新商品分を公表(来年4月適用)
≪解説≫
簡単に言うと、
『厚労省が「新しく登録された福祉用具」についての**全国平均貸与価格と“上限価格”**を公表し、2026年4月からその価格ルールを適用します、という通知です。既存商品のリストを全部作り直すわけじゃない。既存品は従来の公表価格を継続、今回の告示は**“新商品分の価格枠”の追加**に近い。』
福祉用具の“介護保険レンタル(貸与)”と価格の仕組み
介護保険レンタル(貸与)は、要介護者が車いすや特殊寝台みたいな福祉用具を“レンタル”で使える制度。原則1割〜3割が自己負担、残りは介護保険(公費)。負担割合(1~3割)は人によって違う。ケアマネがケアプランに「この人はこの用具」と書き、福祉用具貸与事業所がレンタル・メンテナンスを担当。市場任せにすると値を高く吹っかける事業所が出るので、国は二つの数字を公表している。
- 全国平均貸与価格
全国の実際のレンタル価格データを集計した「だいたいこのくらいで貸してるよ」という相場。
→ これは目安。超えても即アウトではない。 - 上限価格
「ここを超えた額では保険給付しません」という天井ライン。
→ ここを超える見積は、原則保険が効かない。事業所は上限以下に調整するか、別モデルを提案する。
つまり、「平均」は道しるべ、「上限」は絶対超えるなというライン。
なぜ“新商品”だけが時々発表されるのか?
既に世にある商品は、過去にまとめて平均・上限が設定済み。
- 新しく市場に出た型番は、データが溜まり次第、順次「平均・上限」を国が追加で公表する。
- 今回の話は、その“新しく追加された分”の価格ルールを来年4月から適用しますよ、という通知。
介護事業者は「カスハラ対策」を義務化へ
厚労省が10月27日の介護保険部会で、利用者・家族からのカスハラ対応を全ての介護事業者に義務付ける方針を示した。運営基準の見直しが前提。詳細は今後詰めるが、方向性は確定。
≪解説≫
2025年に労働施策総合推進法が改正。事業主にカスハラ防止のための「雇用管理上の必要な措置」を義務付ける。施行は公布から1年6か月以内(規定により一部は2026年度末〜2026年4月施行想定)。介護の運営基準改正はこの国法の流れに合わせる形。
記事はコチラ👉介護ニュースJoint+2CBnews+2、厚生労働省
具体的にやる事
・事業所の基本方針・対処手順の整備と周知
・相談窓口・記録様式の明確化、教育訓練の実施
・受診中止や契約解除を含むエスカレーション基準の明文化自治体・所轄との連携、掲示や同意書での事前告知
これらは既存の厚労省マニュアルや事例集の延長線上にある。BPSD由来の行動は医学的対応で、カスハラは別軸として切り分けるのが原則。
注意事項
- 「費用滞納=カスハラ」ではない。滞納は債務不履行として別処理。滞納時の暴言・脅迫がカスハラ。
- 「家族の強い要求=全部NG」でもない。医療的必要性や安全配慮の範囲は対話で調整、越えたら記録してエスカレ。
「線引きの定義」「エスカレの基準」「記録様式」の三点セットを先に作る。法の完全施行と運営基準の改正が来た時、慌てて作るとだいたい雑になる。今のうちに作って、上司には「法改正に先行対応。事故と離職の予防が目的」と言い切ればいい。ちゃんとやるほど、現場が守られる。あなたも、だ。
過去に勤めていた施設で骨折事故があり、家族から『施設に過失があるので、保険対応で払ってほしい』と強く要望が聞かれる事例があった。保険会社からは、『保険対応ではない』という内容の通知が来たにも拘らず『知り合いの弁護士がいる』という脅しとも取られる発言があった。その家族の訴えや対応がカスハラに該当しないかと行政と相談したが、その時は『今回限り』という念所を家族に書いてもらい、治療代を施設が支払い終息した。介護は信用ビジネスである。施設と家族が普段からどのような関係性を保っているかが問われる。
厚労省「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」「事例集」:定義、線引き、手順のベースはコチラ
介護福祉士 実務者研修時間数一部免除へ
厚労省が、介護福祉士を目指す際の「実務者研修(計450時間)」について、他の国家資格を持つ人の一部時間を免除する方向を示した。対象の例として社会福祉士や保育士が挙がっている。10月20日の専門委員会で提案され、方針として各社が報じた。詳細はこれから詰める段階。
≪解説≫
現行の実務者研修は総時間数450時間。今でも「初任者研修」「旧ヘルパー資格」「基礎研修」などの履修内容は一部科目免除があるが、今後、社会福祉士や保育士といった“他分野の国家資格”による免除も検討中。
対象資格の線引き(社会福祉士・保育士以外にどこまで広げるか)医療的ケアや介護過程Ⅲなどコア科目をどこまで免除対象にするか、これらはまだ“検討入り”。最終決定や施行時期はこれから。焦って誤配信すると恥をかくかもしれない。
記事はこちら👉介護ニュースJoint
記事はコチラ👉厚生労働省
なぜ免除の動きが出たの?
理由は、人材確保が逼迫。他職種から介護へ“回遊”しやすくする導線を増やす狙い。現場で働きながら450時間は重い。
介護福祉士の受験要件は、原則実務経験3年以上+実務者研修修了。今回のニュースは「実務者研修の中身・時間の一部免除」なので、受験要件の骨格はそのまま。免除されても「修了」は必要。短く言うと、他資格持ちに追い風。でもまだ“検討中”。実務者研修そのものは消えないので、社内のキャリア導線と教育費の見直し準備だけ先に進めとけば、あとで慌てない。
記事はコチラ👉SSSC


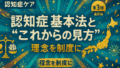
コメント