こんにちは、hiroです。
『変わりゆく認知症ケア』シリーズも今回が最終回となります。
①痴呆→オレンジ | ②新オレンジ→大綱 | ③基本法とこれから
共生社会は約束で終わらせない。基本法の意味と次の一手理念は掲げるだけでは弱い。だからこそ、認知症基本法は「共生社会」を法で固定した。次のステップは、自治体の推進計画に落として可視化し、現場の運用と指標に変えること。この記事は、その橋渡しを最短距離でまとめる。
認知症基本法とは
2023年 認知症の方が尊厳を保ちつつ、希望を持って暮らすことができるように、認知症である方でも認知症ではない方にとってもお互いに認め合い、相互に支えあいながら共生していける社会の実現に向けて新しく法律が制定されました。
正式名称:共生社会の実現を推進するための認知症基本法
成立:2023年6月
施行:2024年1月1日
治す前提から、ともに生きる前提へ。
基本法は、社会の価値観を更新するためのレールだ。レールが敷かれた今、私たちがやることは難しい理想論ではない。本人の声を可視化し、生活のバリアを一つずつ外し、連携の導線を太くする。 小さな実装の積み重ねが、約束を現実に変える最短ルートになる。
認知症基本法の要点
- 目的は「共生社会」。認知症の人が尊厳を保ち、地域で当たり前に暮らせる社会をつくる。
- 国は内閣に推進本部を置き、政府の基本計画を作る。自治体は地域計画を整えて現場実装。
- 基本理念は「人権」「正しい理解の普及」「バリア除去」「社会参加」「意思決定支援」「切れ目ない医療・介護」「家族支援」「研究・予防」。
- 9月21日=認知症の日、9月=認知症月間。啓発を法に位置付け。
- 現場の実務は本人参画の徹底と家族・地域連携の強化がカギ。
キーワードは、共生社会/人権尊重/本人参画/意思決定支援/地域包括/若年性認知症の就労支援/普及啓発/研究と予防認知症の人・家族、支援者、事業者、自治体、国がどの方向に向けて何をするかを定める“土台法”。従来の大綱(方針文書)を超え、法的な枠組みとして共生社会の実現を推進する。
基本理念人権と自己決定:本人の意思・希望を取り出して記録する運用が前提。
- 正しい理解の普及:偏見や誤解を減らす教育・啓発を継続。
- 生活のバリア除去:道順・表示・音・光・支払い動線など環境改善。
- 社会参加:地域活動・働く機会の確保、とくに若年性の方の就労配慮。
- 意思決定支援:選択肢提示→理解支援→同意のプロセスを標準化。
- 切れ目ない支援:医療・介護・地域資源の連携。
- 家族支援:負担軽減、孤立防止、家族会や相談窓口の活用。
- 研究・予防:早期発見、予防、治療法・ケアの質向上。
認知症基本法の要点を“5W1H”でカンタン解説
Who(誰が動くのか)
- 国:推進本部を司令塔に、政府全体の基本計画を策定・進捗管理
- 自治体:地域計画の策定・見直し、当事者・家族参画の場づくり
- 事業者・専門職:意思決定支援、環境改善、家族支援の運用標準化
- 市民・当事者・家族:理解促進、地域活動、意見表明と協働
What(何をするのか)
- 普及啓発と偏見の低減(認知症の日・月間の活用)
- 意思決定支援と権利擁護の仕組み化
- 切れ目ない医療・介護・地域支援の接続
- 若年性認知症の就労支援、社会参加の機会確保
- 生活バリアの除去(表示・動線・音・光・支払い動線など)
- 研究・予防・早期発見の推進
When(いつまでに)
- 国の基本計画のサイクルに合わせ、自治体は計画期間内に年度目標を置き、年次点検
- 9月(認知症月間)に進捗の見える化イベントや市民向け報告を実施
How(どうやって)
- 計画のKPI設定(例:本人参画面談率、家族会紹介率、環境改善項目の是正率)
- 協議の場に当事者・家族・事業者・行政が同席し、課題と改善案を四半期ごとにレビュー
- 施設・包括・医療・就労支援を地域連携図で可視化し、相談導線を一本化
Why(根拠)
- 基本法により、これらは努力目標ではなく政策の土台に。自治体・事業者の責務や計画策定が制度上の位置づけを得た
How much/How well(評価)
- 年次の自己点検票と外部評価(住民アンケート・ヒアリング)
- 相談経路のリードタイム、本人の意思反映率、BPSD関連の非薬物介入割合などをKPIに
現場での“変化の実感”ポイント
正直、掲げる言葉は似てますよね。でも、文言の格上げは運用チェックの進み方を変える。
たとえば:
- 相談員・ケアマネ側は、**「本人の意思記録」**の独立欄や選択肢提示の手順を様式化しないと監査・評価で突っ込まれやすい。これは法の理念が根拠になる。
- 自治体は計画への当事者参画の形を設計せざるをえない。会議体の設置や意見反映の仕組みづくりが、単なる“努力”の域を超える。
- 9月の啓発月間は、施設・包括・自治体の連動イベントが“恒例化”しやすくなり、広報や連携の予算立ても通りやすい。
これからの見方(視点のアップデート)
BPSDを「ご本人の困りごとの表現」と読む変える
- 行動そのものを『困りごと』として抑えるのではなく、未充足ニーズの表現として解釈する
- 具体例:発語が増えた→「安心の欠乏」と仮説を設定、徘徊→「目的地・役割探し」と仮説を設定する など
- 対応としては「環境を調整する+役割を与える+ご本人が安心した状態になるように整える」を組み合わせる
読者行動(すぐできるアクション)
A. 本人会・家族会の探し方
- 自治体サイトで「認知症カフェ/家族会」を検索
- 地域包括支援センターに最寄りリストを依頼
B. 認知症カフェの立ち上げ(超要約)
- 目的を一文で:例「本人と家族が安心して話せる場を月1回つくる」
- 場所:公民館・寺社・カフェの空き時間など、静かで分かりやすい動線
- 運営:地域包括+ボランティア+事業者で小さく始める
- メニュー:お茶+10分レク+自由対話。情報提供は一テーマ10分以内
- 安全配慮:初回に連絡先・体調確認、緊急時動線の共有
- 評価:参加者アンケート3問(満足度/安心感/次回要望)
C. 権利擁護の連絡先ミニ一覧
- 地域包括支援センター:総合相談・関係機関連携の窓口
- 成年後見・日常生活自立支援:社会福祉協議会や弁護士会の窓口
- 消費者被害:消費生活センター
- 虐待・重大リスク:自治体の高齢者虐待防止担当、警察の緊急通報
- 医療・緊急:かかりつけ医、訪問看護、救急受診案内
これまでとの違い(大綱と基本法は何が違うのか)
認知症基本法とこれまで新オレンジプラン、認知症施策推進大綱などの基本的な考え方が似ている部分がある事にお気づきででしょうか?
以下は、何が違うのかを解説していきます。
同じこと
目指す方向は継続。偏見を減らす、切れ目ない支援、家族・就労支援、研究推進などの柱はオレンジ時代から連続している。
違うこと
・法律に格上げ
2019年の「大綱」は方針文書だったが、今は法律。国・自治体・事業者の責務や計画の枠組みを条文で明記。これは「やるやる宣言」から「法で担保」への移行。啓発の日・月間を法で明記し、社会全体の関心を継続的に喚起。
・ガバナンスの明確化
内閣に認知症施策推進本部を置き、政府の基本計画を作り、自治体計画につなげる階層化を法定。縦割りを越える司令塔の位置づけが、通知じゃなく法レベルになった。
・本人参画と意思決定支援の“必須級”化
当事者・家族の参画を計画作成プロセスに埋め込み、意思決定支援を理念の芯に据えた。現場では「家族代弁だけでOK」が通らなくなる方向。
・啓発の法定化
9月21日=認知症の日、9月=認知症月間を法律に明記。毎年の官民連動イベントを回すための“スイッチ”を法で固定した。
・若年性認知症や就労の扱いを明文化
働く権利や支援の接続を、理念や計画の中でよりはっきり書き込んだ。雇用領域との橋渡しが“努力目標”から“計画事項”に寄る。
まとめ
オレンジ時代は「いいことやろう」が中心であった。基本法後は「やる体制を法で固める」にシフトする。メニューは似てても、責任の所在と実装の必然性が違う。
つまり、看板は既視感あっても“やらざるを得ない度”が一段上がってる。人手が足りないのに仕事だけ増える理不尽、知ってる。だからこそ、様式・連携・啓発の使い回しテンプレで省エネ実装するのが現場の生存戦略。
認知症基本法は、現場に“新しいやること”を大量に追加する法律ではなく、本人参画と地域連携を当たり前にするための道筋を明文化したもの。できるところから、様式・環境・連携の小さな改良を積み上げることが最大の実装です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 認知症基本法は“新しい介護給付”を作る法律?
A. いいえ。給付の枠組みを直接変える法律ではなく、方針・体制・計画・役割分担を定める“土台法”。
Q2. 自治体は何をすればいい?
A. 地域計画を整え、当事者・家族が参画する場を設計。啓発、バリア除去、就労配慮、意思決定支援などの実装を推進。
Q3. 事業所は何から始める?
A. 面談様式と運用の見直し(本人の意思欄を独立)、意思決定支援チェックリスト、家族支援の同意連携、環境点検のPDCA化。
Q4. 若年性認知症の就労はどこに相談?
A. ハローワークの専門窓口や地域の就労支援機関、自治体の就労相談。家族の就労・経済相談も並行して案内。
参考・公的情報(概要)
- 法律本文(e-Gov)
- 厚生労働省「認知症基本法」概要資料
- 認知症施策推進本部・関係者会議(内閣官房)
- 認知症の日(9/21)・認知症月間(9月)に関する広報
- 新オレンジプラン 概要資料
- 認知症施策推進大綱(2019)
- 認知症基本法
〇参考書籍:
★『おはよう21』2025年5月号「深刻化する人材不足と求められるケアの質 これからどうなる?介護保険制度」
★『おはよう21』2024年7月号「これだけは押さえたい 認知症の医療・ケア・制度・重要ワード80」
★定期購読はコチラ
〇関連記事
✔【認知症ケア】名前が変わるとケアが変わる。認知症という言葉の誕生 | 介護しよ.net
✔【認知症ケア|第2部】 新オレンジプランから認知症施策推進大綱へ:連続とアップデートを“現場語”で解説 | 介護しよ.net
✔認知症について解説しています。 | 介護しよ.net
〇介護情報誌『おはよう21』~1冊から購入できますが、定期購読がおすすめです~
- バックナンバーのデジタル版が見放題
- 最新号が毎月届くので買い忘れなし
- 継続的に学びが積み重なり、スキルアップにつながる
〇 noteを始めました。
こちらでは介護に留まらず、私が普段思う事や、趣味など自由な内容を記事にしていきますので、
こちらから!👉hiro|note
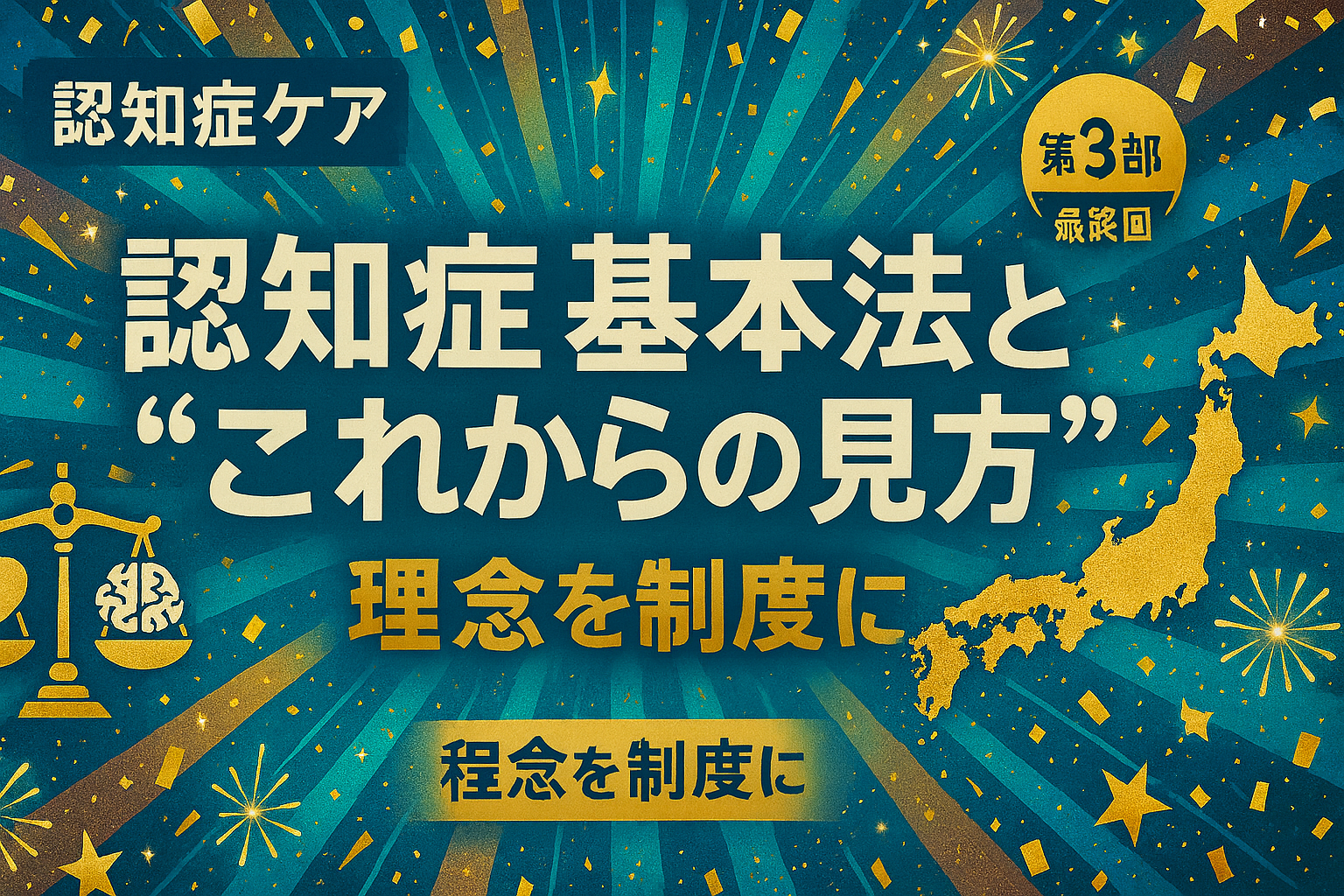


コメント