こんにちは、hiroです。
介護施設で働いている皆さんは、処遇改善手当を受け取っていますか?
また、利用者やご家族の方は、請求書に「処遇改善加算」という見慣れない項目を目にして「これは何だろう?」と思ったことはないでしょうか。
処遇改善手当は、低賃金とされてきた介護職員の給料を少しでも引き上げるために、2009年から国が各施設へ交付を始めた制度です。
しかし、この仕組みはその後、大きな変化を遂げました。以前は国からの「交付」でしたが、現在は介護報酬に「加算」として組み込まれ、利用者の自己負担にも影響する形に変わったのです。
今回は、この処遇改善の歴史と「交付」から「加算」に移行した理由を分かりやすく整理してみます。
介護職員処遇改善の歴史
2009年:処遇改善交付金のスタート
介護職員の低賃金と人材不足が深刻化したことを受け、国は「処遇改善交付金」を創設しました。
ただしこれはあくまで時限的な補助金で、毎年の予算措置に左右される不安定な仕組みでした。
2012年:処遇改善加算の創設
交付金を廃止し、介護報酬に「処遇改善加算」として組み込みました。
事業所が算定するには、職員の賃金改善計画を作成し、実際に反映することが条件に。制度として恒久化されたのです。
2015年:加算区分の整理
加算区分がⅠ~Ⅴに分かれ、要件も整理されました。
これにより幅広い事業所が活用しやすくなり、処遇改善が現場に届きやすい仕組みへ。
2019年:特定処遇改善加算
「経験・技能のある介護職員」をさらに厚遇するために創設されました。
長年現場を支える介護福祉士を中心に、キャリアを積むほど評価される仕組みです。
2022年~:ベースアップ等支援加算
単発的な改善ではなく、給与水準そのものを底上げする目的で導入されました。
他産業と比較しても遜色ない水準をめざす取り組みです。
なぜ創設されたのか?
- 人材不足の深刻化:介護ニーズは増える一方で「きつい・安い・将来性がない」と敬遠されがちでした。
- 離職率の高さ:低賃金のままでは人材が定着せず、現場の疲弊につながりました。
- 制度の維持:介護保険制度を維持するには、介護職員の確保が不可欠でした。
- 専門職としての評価:介護は専門性の高い仕事であり、その社会的評価を処遇に反映させる必要がありました。
手当から加算へ ― その理由とは?
「財政が厳しいから」だけではありません。
- 恒久化のため
交付金は時限的な補助で安定性に欠けていました。加算として報酬に組み込むことで、制度を恒久化できました。 - 事業者の責任を明確化
交付金時代は「本当に賃金に回っているのか?」が不透明でした。加算方式なら、事業所は計画を立て、確実に職員に反映する責任を負います。 - 財政的なコントロール
交付金は国の特別予算で全額負担でしたが、加算にすれば介護報酬の枠内で安定的に財源を確保できます。
特徴①:以前の「交付」方式
国から事業所に直接「処遇改善交付金」が支給され、職員の給料アップに充てられていました。
利用者や家族は、このお金について意識することはほとんどなかったのが特徴です。
特徴②:現在の「加算」方式
2012年以降は、介護報酬に「処遇改善加算」として組み込まれました。
その結果、利用者の請求書に「処遇改善加算」という項目が載るようになり、利用者負担にも直結する仕組みとなりました。
特徴③:変化がもたらした影響
介護職員への影響
- 給与改善はありがたいが、「利用者さんの負担で成り立っている」と意識するようになった。
- 事業所によっては加算を算定しない選択もあり、恩恵に差が出ることも。
利用者・家族への影響
- 「いつのまにか請求額が上がっている」と感じる人も。
- 加算が何に使われているのか、分かりにくいと不満につながる場合がある。
事業所への影響
- 加算の計画書や実績報告の事務負担が増大。
- 利用者や家族からの説明責任も問われるようになった。
まとめとこれから
処遇改善手当は「交付」から「加算」へ移行し、制度としては安定しましたが、その分利用者負担という形で現れるようになりました。
介護職員にとっては生活を支える大切な収入源であり、利用者にとってはサービス費用の一部でもあります。
私自身、給与明細を見ると「基本給は低い」と感じることがありますが、処遇改善手当があることで全体の手取りは確かに増えています。ありがたい半面、「これは利用者さんのお金でもある」という意識は常に持っていたいと思います。
処遇改善手当は、単なる賃金の話ではなく、介護の未来を支える仕組みそのものです。
制度を理解し、現場・利用者・行政がそれぞれの立場から考え続けることが、より良い介護につながるのではないでしょうか。
〇関連記事
✔ケアマネ不足は本当?現場の声と試験制度から見る最新事情 | 介護しよ.net/blog
✔介護業界の今がわかる!週刊介護News(11月7日版) | 介護しよ.net/blog
✔【前編】介護保険制度の改正の歴史 ~創設から予防・地域支援2000→2015~ | 介護しよ.net/blog
〇介護情報誌『おはよう21』~1冊から購入できますが、定期購読がおすすめです~
- バックナンバーのデジタル版が見放題
- 最新号が毎月届くので買い忘れなし
- 継続的に学びが積み重なり、スキルアップにつながる
〇 noteを始めました。
こちらでは介護に留まらず、私が普段思う事や、趣味など自由な内容を記事にしていきますので、
こちらから!👉hiro|note


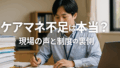
コメント