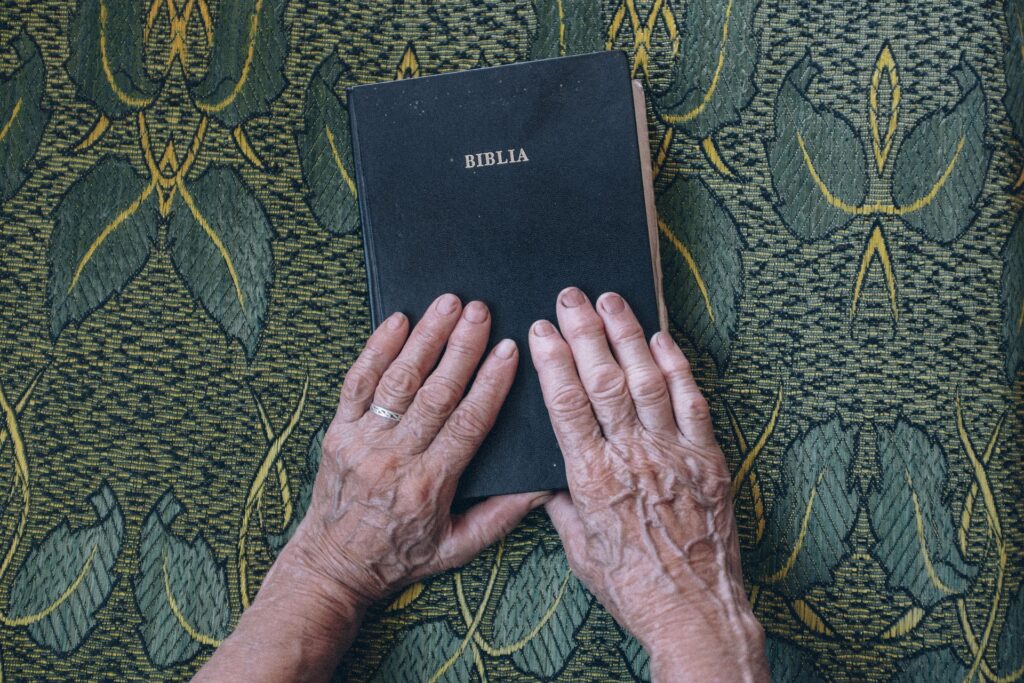
✔介護保険の仕組みを解説
みなさん、こんにちは!
hiroです。
今回は介護保険についての内容です。
★介護保険はどのようなものか?
★介護保険の申請方法は?
★介護サービスを受けるにはどうすればよい?
介護保険と言う言葉は知っていても、制度の事や申請方法などがわからないと思う方は、意外と多いのではないでしょうか?
私は介護職をしていますが、介護保険についてよく知りませんでした。
私の過去の話ですが、介護とは違うコミュニティにいた時、私が介護職をやっていると伝えた所、
『実は、うちの母が介護が必要になってきたので、介護保険というのを申し込もうとおもっているんだけど、どこに行けばよいかわからなくて。まず何をすればよいの?』
と聞かれました。しかし、その時は、『まず市役所に行けば申請できますよ』と答えましたが、明確には答えられませんでした。
そんな反省を生かして、今回は介護保険制度の確認と手続き方法について共有したいと思います。
私は、介護職を約20年勤めていて、現在も特別養護老人ホームで働いています。
長い介護職生活で感じたことや経験を一人でも多くの方と共有したいと思い、こちらのブログを運営しています。
長い介護職経験がある中で、介護保険について理解できていなかったことは私としては、とても恥ずかしい事と反省し、今回の内容をお伝えしたいと思います。
この記事を最後までお読みいただければ、介護保険制度の大枠と申請についてが理解できると思います。
なお、今回は制度の大枠をお伝えするので、細かい内容に関しては割愛いたしますのでご了承ください。
- 介護保険制度とは?
- 介護保険申請の流れ
- 誰が対象?第1号・第2号の違い
- 地域包括支援センターとは?
- 要介護と要支援の違い
- 非該当になった場合の対応
- ケアマネとの連携
1,介護保険制度とは?
🔶介護保険とは、西暦2000年から始まった制度で、たくさんの介護サービス業者から、自分にあった介護サービスをから自分で選べる制度です。
実は、2000年以前にも、介護サービスはありました。
しかし、その時代は措置制度と言って、行政がどのサービスを受けるかを決めていました。
AさんがB社のサービスを受けたいと思っていても、行政側がC社でお願いします、と言われ、行政が決めたサービスを受けるしかなかったのです。
サービス自体も、競争がないため、どこへ行っても同じという画一的なサービスでした。
しかし、時代の変化とともに、そのような制度が長続きするわけもなく、2000年に新しい制度が始まりました。
これが、介護保険制度の歴史です。
2,介護保険申請の流れ
一般的な保険を使う為に手続きが必要なのと一緒で、介護保険を使用するためには手続きが必要です。
介護保険の申請は申請者がお住いの市町村で行います。
市町村の担当者に状況を説明して、申請書に必要事項を記載し、一か月ほど待つと結果が得られるというのが一般的な流れです。
3,誰が対象?第1号・第2号の違い
🔶介護保険には
第1号被保険者と第2号被保険者があります
・第1号被保険者とは、65歳以上の方です。
・第2号被保険者とは、医療保険に入っている40歳から65歳までの方で、指定された難病にかかっている方です。
介護保険申請は、65歳以上であれば誰でも申請できますが、若い人が申請するには条件を満たす必要があるという事ですね。
4,地域包括支援センターとは?
先に市町村で申請できるとお伝えしましたが、市町村とは具体的に言うと市役所、区役所、役場の事です。
★東京23区の場合 → 各区役所(例:世田谷区役所)
★市に住んでいる場合 → 市役所(例:横浜市役所)
★町や村に住んでいる場合 → 町役場・村役場
しかし、実際は上記の場所に行く人はごく一部で、大抵の方が、地域包括支援センターで申請されます。
『地域包括支援センター』
🔶地域包括支援センターとは、
概ね中学校区ごとに1か所以上 設置されており、利用者にとって「歩いて通える距離」を目安に設置されています。
つまり、大きな市や町では複数のセンターがあり、自分の住んでいる担当エリアのセンターが決まっています。
地域包括支援センターは、市町村が設置し、身近な地域(中学校区ごと)に1か所以上設けられています。
そして、実際の運営は、福祉法人・医療機関・社会福祉協議会などが委託されて行っています。
例を挙げますと、
○○地域包括支援センターの運営は、『特別養護老人ホーム 〇〇〇〇』が運営しているという形です。
申請をしたら、約一か月くらいで、手元に介護保険証が届くと思います。
ケアマネージャーとすでに関りがある場合は、事業所から連絡が来るかもしれませんね
5,要介護と要支援の違い
🔶要介護とは、何かしらの介護を継続して要すると見込まれる状態の事を言います。
介護保険証には、要介護1~5まであり、要介護○と記載されます。
介護度は要介護1が一番軽く、軽介助が必要で、要介護5が一番重く、常に介助が必要、という意味です。
介護度によって、使用できるサービスの幅が違うので、注意が必要です。
要介護が重いほうが、より多くのサービスを保険内で使用できます。
判定方法は、市町村職員が対象者の生活状況やできる事、できない事をチェックリストで確認して、主治医の意見も取り入れながら総合的に判断し決定するため、意図的に重い介護度を出すことはできない仕組みになっています。
ただ、要介護1,2は比較的身の回りの事は自身でできる方が多く、多くの介護サービスは必要とされない方が多いです。
また、認知症の程度も介護度を決定するうえで、大きな要因となります。
介護保険は、介護度によって決められたサービスを選んで使用できますが、青天井に使用できるわけではありません。
介護サービスを使用する際、完全無料と言うわけではなく、基本1割負担で利用する形になります。
※収入がある方は、2割、もしくは3割負担となります
6,非該当になった場合の対応
介護保険を申請すれば、必ず要介護となる、というわけではありません。
介護保険の認定結果が「非該当」または「要支援1・2」となる場合もあります。
要介護に至らない場合、要支援という枠組みがあります。
🔶要支援は、要支援1と要支援2があります。
要介護同様で、要支援1が一番軽いという意味になります。
✔ ケース①:認定結果が「非該当」の場合
🔶「非該当」とは?
介護保険のサービスを利用するには、要支援・要介護の認定が必要ですが、
本人の心身の状態が「まだ軽い」と判断された場合、要支援にも該当しない=非該当となります。
🔶非該当でも利用できる支援
支援の種類 内容
✔ 市区町村の一般介護予防事業 「元気なうちから支援しよう」という軽度者向けサービス。
介護予防教室、通いの場(サロン)、配食サービス、見守りなど。
✔ 地域包括支援センターでの継続的な見守り・相談 生活状況の変化があれば、再申請の助言などをしてくれる。
✔ 地域のボランティア支援や生活支援体制づくり事業 ごみ出し支援、買い物同行など、地域資源を活用した支援も。
🔔ポイント
「介護保険のサービス」は使えないが、「地域の支援」は活用できる
体調や生活状況が変わった場合は、数か月後に再申請も可能
✔ ケース②:認定結果が「要支援1・2」の場合
🔶「要支援」とは?
日常生活のほとんどは自立しているが、一部に介助や見守りが必要な状態
「介護予防サービス」が対象となります
🔶要支援の場合の次のステップ
ステップ 内容
① 地域包括支援センターへ連絡 要支援の方のケアプラン作成は、地域包括支援センターが担当です。
(※一部の民間事業者に委託している場合あり)
② ケアプラン(介護予防ケアプラン)の作成し、どのサービスを、週に○回使用するかなどを相談して決めます。
③ サービス利用開始 訪問型サービス、通所型サービス、福祉用具貸与などが利用可能
🔶利用できる主なサービス(要支援共通)
サービス種別 内容
★ 訪問型サービス 生活援助中心のヘルパー支援(掃除・調理など)
★ 通所型サービス デイサービス、機能訓練特化型デイなど
★ 福祉用具貸与 手すり・歩行器など(レンタル)
★ 介護予防教室 転倒予防や運動、栄養指導など
🔶 非該当 市町村の介護予防事業や地域支援を利用。
再申請も可能。
✔ 要支援1・2 地域包括支援センターでケアプランを作成し、
介護予防サービスを利用。
7,ケアマネとの連携
介護サービスを使用するには、ケアマネージャ―と相談してサービスを選択して形が一般的です。
現在、介護保険のサービス事業者は多数存在し、どの事業所も良いサービス業者ではありますが、それぞれ力を入れている所が違っていたりする事と、介護度に応じて使用できる単位が違ってきます。単位を超えてしまうと、支払いが自費になってしまうので注意が必要です。
わからない場合は、地域包括支援センターへ行けばケアマネージャーを紹介してもらうこともできるので、相談に行くことをお勧めします。
★以下のPDFは、実際に使用されている申請書です。
申請は、各市町村により違うので、自身の地域にお問い合わせください。
↓
〇 介護しよ.netの公式Lineを作成しました。
介護歴20年のhiroが、介護とお金のギモンに家族目線で答えます。
今なら、登録いただいた方に
『介護のお金で損しない:まず確認する 7 項目チェック』を無料ダウンロードできます。
Line登録はコチラから👇
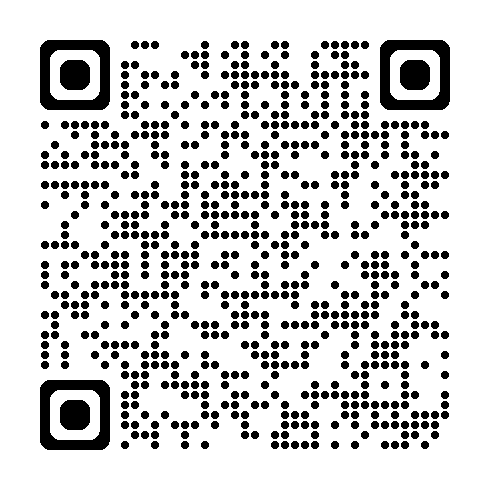



コメント