はじめに
こんにちは、hiroです。
今回は、日本の国民皆保険制度について、その歴史と背景をご紹介します。
私たち日本に住む人は、病気やケガをしたときに医療費の一部を支払うだけで治療を受けられます。これは、1961年に実現した国民皆保険制度(Universal Health Insurance)のおかげです。しかし、最初からこの仕組みがあったわけではありません。では、なぜこの制度は始まったのでしょうか?
📌 なぜ国民皆保険制度は始まったのか
戦後の日本では、多くの人が医療を受けられない状況でした。特に農村部や自営業者は、医療保険に入っていない人が多く、病気になってもお金がなくて受診できず、重症化や死亡する例が後を絶ちませんでした。
この状況を変えるため、政府は「誰もが医療を受けられる仕組み」を整える必要があると考えました。
主な背景は次のとおりです。
- 🏚 戦後の貧困と無保険者の多さ
医療費は全額自己負担が基本で、病院に行けない人が多かった。 - ⚒ 健康な労働力の確保(経済成長のため)
病気で働けない人が増えると、生産力が低下して経済発展が遅れる。 - 🏛 社会保障制度の充実
厚生省が「国民全員を何らかの保険に加入させる」目標を掲げた。 - 🌍 国際的潮流の影響
国際労働機関(ILO)や世界保健機関(WHO)など、社会保障の整備を推奨する動きが世界で広がっていた。
🏥 国民皆保険制度ができるまでの流れ
- 1922年:健康保険法制定(1927年施行)
→ 都市部の工場労働者など一部の被用者を対象とした制度がスタート - 1938年:国民健康保険法制定(1939年施行)
→ 主に農村部住民を対象。ただし任意加入で、無保険者はまだ多い - 1958年:国民健康保険法改正
→ 市町村に国民健康保険(国保)を設置することを義務化 - 1961年:国民皆保険制度実現
→ すべての国民が職域保険(被用者保険)か地域保険(国保)のいずれかに加入
→ 同年、国民皆年金制度も実現
このようにして、1961年に日本は「病気になったとき、誰でも必要な医療を受けられる社会」をつくり上げました。
🌸 制度の意義とこれから
国民皆保険制度は、誰もが安心して暮らせる社会を支える土台となりました。
高齢化や医療費の増大など課題もありますが、日本の医療制度は世界的にも高く評価されています。
- 医療機関にいつでも自由にアクセスできる
- 所得に応じた保険料で公平に医療を受けられる
- 病気やけががあっても生活が破綻しない
✍️ まとめ
国民皆保険制度は、
「貧困層にも医療を」「国民の健康を守り経済発展を支える」「世界基準に追いつく」
という強い社会的・経済的な要請から生まれた制度です。
当たり前に思える日本の保険も、色々な歴史があって今があるのだな、と感じています。
次回は、日本の保険システムと似ているイギリスの保険事情と日本を比べてみようと思います。
同じようで違う保険システムをたっぷり解説いたします。
また、次回もお楽しみに!!
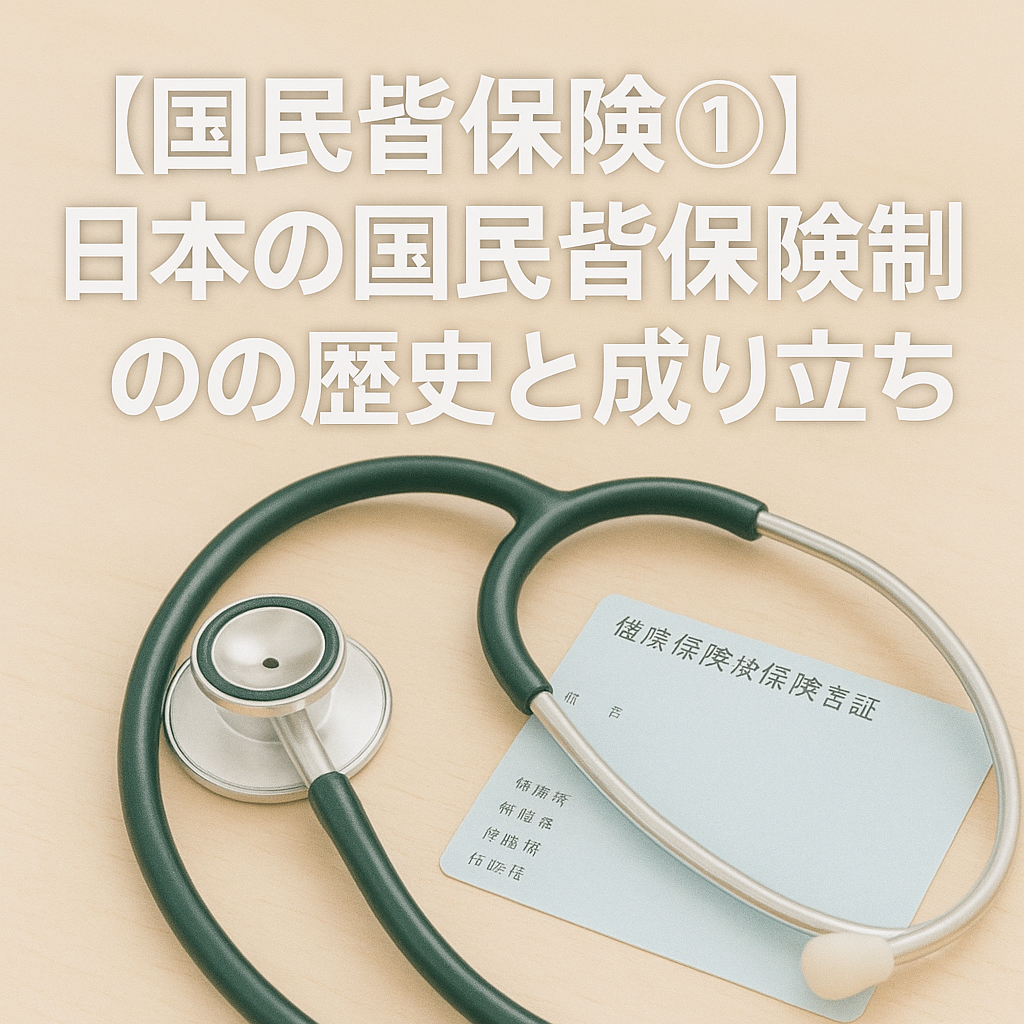
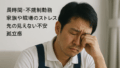

コメント