
こんにちは、hiroです。
今回は、「介護とは?」というテーマです。
とても抽象的な質問ですので、「あなたにとって介護とは何ですか?」と聞かれた時、困ってしまいますね。
私の場合は、
・介護とは、尊い仕事である
・介護とは、大変な仕事である
・介護とは、楽しい仕事です。
と答えるかなと思います。
どこに重きを置くか人それぞれですし、考え方、捉え方も違うため、答えは正解はないと思います。
今回は、最近、『介護とは?』について考える機会があったため、この機会を使い、私の考えを述べていきたいと思います。
私は、介護職を18年間しており、現在も特別養護老人ホームにて働いています。長い介護経験を活かし、知識や情報を提供する事で何かの役に立てばと思い、このブログを運営しております。
どうぞ最後までご覧ください。
介護とは
介護と聞いて、頭に思い浮かぶものは何でしょうか?
「介護」という言葉の始まりは、1963年に「老人福祉法」が制定され、特別養護老人ホームで家族や親
族に代わり、お年寄りの身の回りのお世話をする人のことを「寮母」と呼び、その寮母の業務を「介
護」と呼んだことがきっかけです。私の働いている施設で、各フロアの事務所は「寮母室」と呼ばれていますので納得です。
介護の理想は、『できることは利用者自身でやって頂き、出来ない所を手伝う』です。
そして、介護は食事、入浴、排せつなど、様々な生活行為に手助けが必要な人に援助し、生きる意欲を引き出すことも大切と言われています。
ここで一つ例を挙げたいと思います。
・Aさん:更衣介助の時、動作がゆっくりだけど自身で更衣できるので、職員がそばで見守りをし
て出来ない所(肘や頭を通すのを手伝う。衣服を用意する)を手伝う。見守りだけをしていると5分強かかる。
・Bさん:食堂から居室へは歩いて行けるので、職員が付き添って歩いてもらう。しかし、時間は1
0分近くかかる。
上記の対応が『できることは利用者自身でやって頂き、出来ない所を手伝う』介護のあるべき姿です。
しかし、現場からは、『そんなに時間をかけていられない、無理だ!!』
という声が聞こえてきそうですね(笑)
先ほどの例を実情に合わせますと
Aさん:職員が更衣介助を手伝い、3分で終わらせる
Bさん:利用者に車いすに乗っていただき、職員が車いすを押してしまう
少し極端な例ではありますが、今までの介護経験上、このような対応をしていることが多かったです。
一方で、『そんなに時間をかけていられない、無理だ!!』という現場の声を聞いて、
『なんでできないんだ?できることはやって頂く介護をやってください』
と怒る人もいます。特に管理職や介護への信念が強い方に多いです。
そのような言い方をする方は、介護職の経験が浅いか、未経験で実情を知らない方が多かったように感じます。
私はずっと現場にいましたので、理想と現実は違いを強く感じます。
介護の理想通りにやりたいと思っている職員もたくさんいますが、そのような対応ですと、現場は回らないのが現実です。
そこで、必要なのが、
工夫する事です。
ある現場では、『利用者自身でできる人はできる所までやって頂いて、その間に職員は他の利用者の介助へ行く』
という具合に工夫していました。
介護は「工夫」がとても大切です。
介護現場の一例をあげましたが、他の問題に対しても同様で工夫が大切と思っています。
今、私の施設では、
・車いすの清掃が出来ていない事
・残業の問題
・夜勤の動きの問題
・介護物品が不足している
など問題として上がっていましたが、工夫をすることで解決に至りました。
・車いすの清掃が出来ていない事
➡夜勤者が一日一台、車いすを拭く仕組みを作った
・残業の問題
➡画一的なケアを見直し、必要な方に必要なタイミングでサービスを提供することで解決への方向性が見えてきた
・夜勤の動きの問題
➡夜間帯の業務のスケジュールを見直し、日勤でできる夜勤業務は日勤に回す
・介護物品が不足している
➡今すぐ購入が難しいものは、代替品を検討する
実現するためにどのような工夫が必要なのかを考え、試行錯誤していくことが介護の面白さの一つでもあります。
介護の歴史
介護職は、かつて「リストラの受け皿」と言われた時代がありました。
また、芸能人が罪の償いとして介護現場で働くとニュースにもなりました。
それを見聞きして、私も介護職を馬鹿にしているのか!と憤りを覚えました。
当時、『介護は誰でもできる簡単な仕事で、弱者へ奉仕する事は良い事』、という印象を持たれていたからかもしれません。
しかし、私自身も、なんとなくつなぎのバイト感覚で介護を始めました。
ただ、介護職を続けると結構、奥深いことにも気づきました。
・一緒にトランプをして遊ぶことも仕事
・介護の食事介助はリスクがあり、人によって介助の仕方を変える必要がある
・食後の配薬は、一つ間違えば命に奪う事故に至ってしまう
など、大変な仕事だとだんだん気づきました。
変わりゆく介護業界
初めて介護職員として入職した施設は医療色が強く、喀痰吸引を介護職員が行っていた時代でした。
私自身も当時の主治医に喀痰吸引の手順を教わり、看護師が不在の夜間帯に痰を吸引していました。
現在は制度が変わり、介護職が喀痰吸引をする為には、資格を取り、医師の指示書がある場合のみ喀痰吸引が可能となっています。
その他に変わったことと言えば、OKだったものがNGになった例もありました。
・胃ろうの方に栄養剤を流すことを介護職がやっていました
・手にはミトンを装着したり、つなぎ服を着せる事も上司の指示で行っていました。
今後も介護業界は変化し続けていくことが考えられるので、介護職員は変化に対する柔軟性が求められています。
しかし、変化って怖いですよね?
私自身も同様で、「以前はこうだった」と声高に言っていたこともあります。
ある研究で
「人は誰でも変化を嫌い、現状維持を保とうとする傾向がある」
と、証明されているそうです。
人によっては変化することに強いストレスを感じることもあるかと思います。
新しい事を習慣化するまでは毎日少しずつ取り組んだとしても最低21日かかると言われています。
習慣にするまでは忍耐が必要ですが、習慣にしてしまえばそれが当たり前になるのでストレスに感じなくなることも証明されています。
介護職は認知症の理解が大切
介護職をする上で、認知症について知ることはとても重要です。
認知症には
・アルツハイマー型
・血管性認知症
・レビー小体認知症
と種類が存在します。
過去にいた現場で、認知症の方との関わり方に『?』が付く職員がいました。
・ナースコールを何度も押す利用者に対して「何回押せば気が済むんですか?」と怒鳴っていた
・同じことを繰り返ししている認知症の方に、なぜダメなのかの理由を何度も伝えて説得をしようと
していた。
認知症への理解が足りない事と高齢者虐待に引っかかるのではないか?とも取れる内容です。
また、『認知症の方も1人の人間なので、嘘を言うのはおかしいのではないか?』
という意見も聞いたことがありました。
介護職としては、相手の方が安心できるような声かけやその方の世界に合わせる時などの嘘はOKなのではないか?と考えています。
本当の事を伝えることで、相手の方が落ち着く状況でしたら、真実を伝える対応が正解なのかもしれません。
最後に
冒頭にも書きましたが、介護に答えはないと思っています。
究極を言うと、相手の方が安心、安全に感じてもらえばOKかなと考えています。
答えのないところが、介護の楽しさであるという事は、ずっと自論として持っています。
もう一つの自論として、自己満介護は避けたいというものもあります。
自己満介護とは、理想の介護を求めて、一人の利用者だけに手厚い介護を提供する事を定義としています。
チーム全員が同じ介護方法なら良いですが、単独で自己満介護をしてしまうと、チームの輪が壊れるだけでなく、待っている利用者をさらに待たせてしまう事もあるので避けたいと思っています。
今回は、介護とは?について自論を述べて参りました。
何かお役に立てたら幸いです。
また、次回をお楽しみに!!
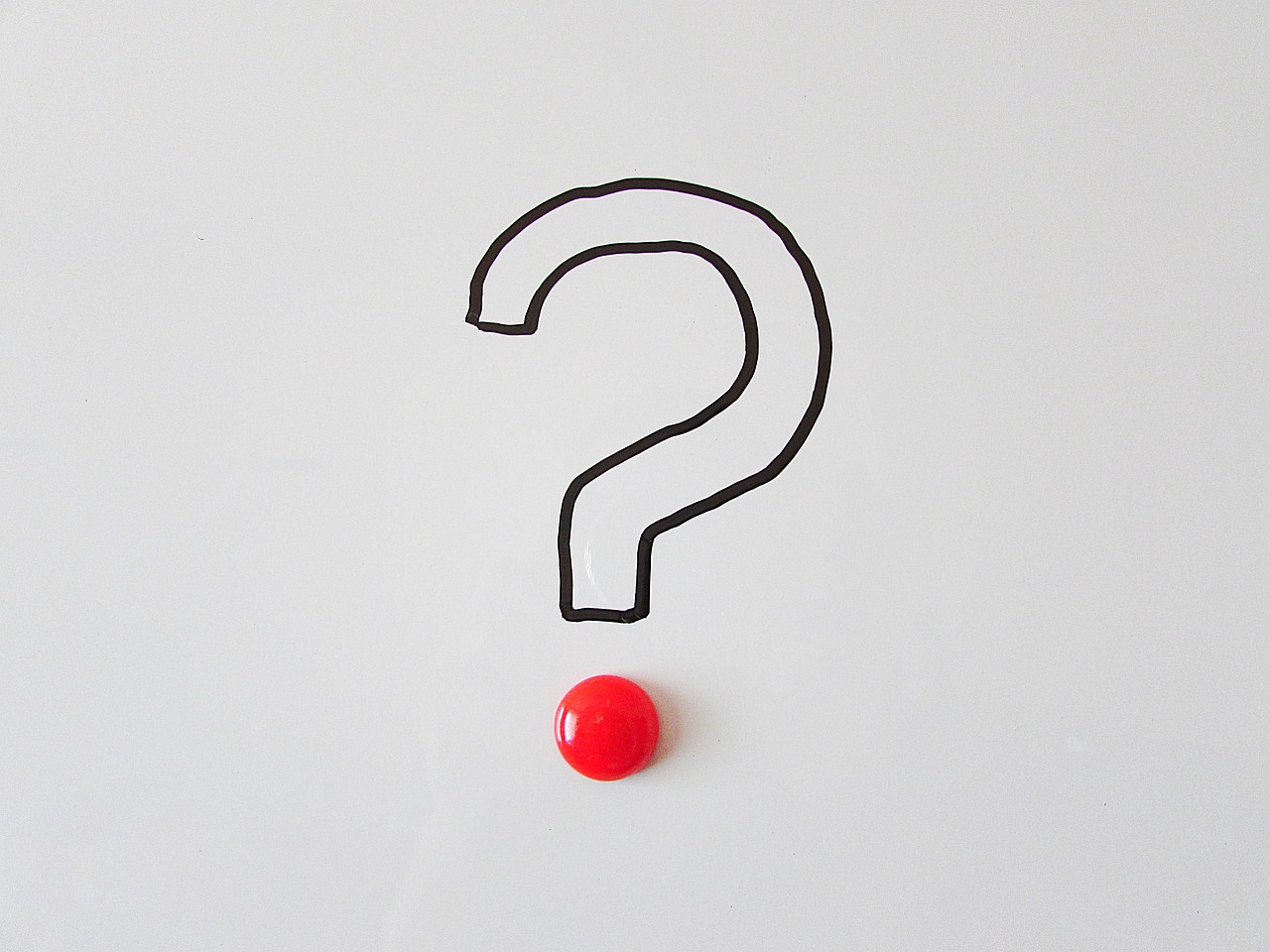


コメント